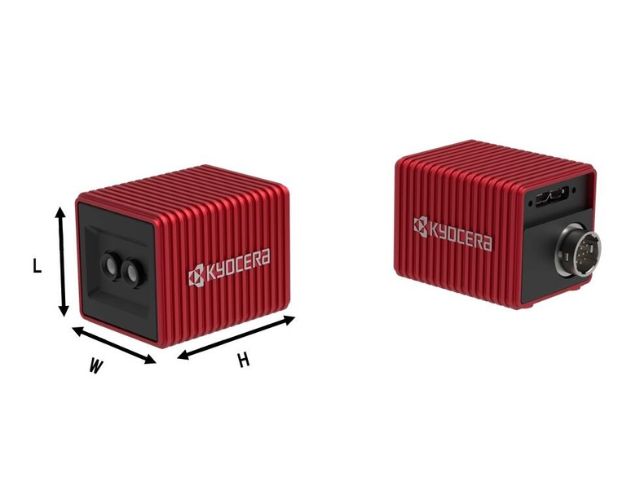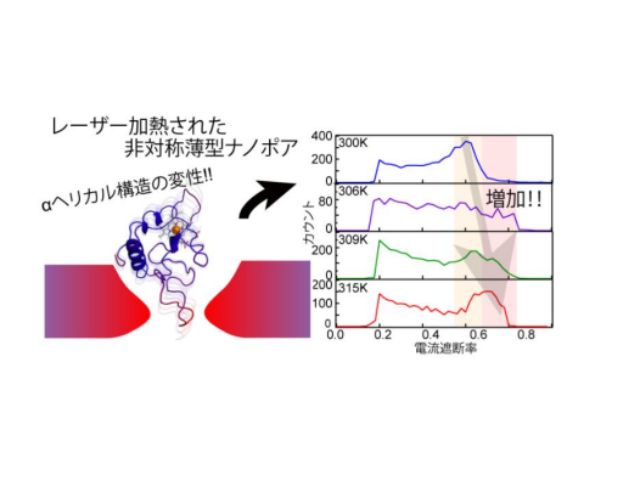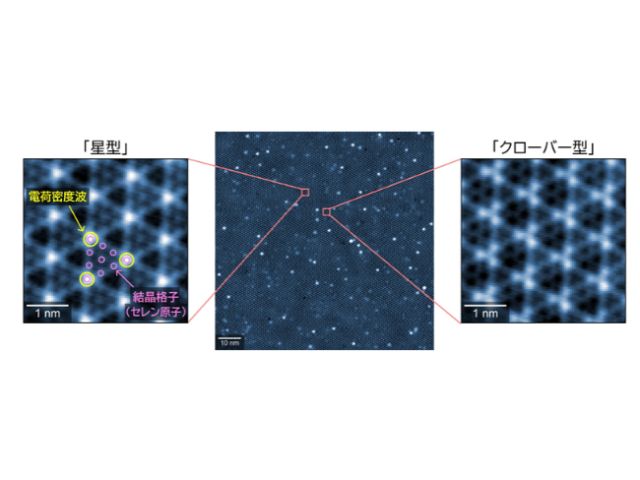埼玉大学と東京大学は、高性能なレーザー計測技術により、放電発生初期の超高速現象(ストリーマ放電)を支配する主要パラメーター群をセットで直接計測することに成功した(ニュースリリース)。

放電は次世代半導体の製造プロセスや宇宙機の推進機構といった現代科学の最先端で活用されている。ここで、放電の一種であるストリーマ放電は雷の前駆体として知られており、自然現象として重要となっている。
ストリーマ放電の内部では、電界で加速された電子が雰囲気気体と衝突することで解離・電離・励起・付着といった多彩な反応が起こり、放電の物理・化学的な特性が決定される。そのため、電子の数と電界はストリーマ放電のダイナミクスを司る最も重要なパラメーター。
しかし、ストリーマ放電は形状に再現性が無く、ナノ秒で経時変化する超高速現象であるため、これらを直接計測することは極めて困難だった。そのため多くの従来研究では理論・数値計算モデルにより電子密度と電界を予測してきたが、実験による検証は皆無だった。
この想と実のギャップを埋めモデルの信頼性を向上させるためには、これまで捉えることができなかった電子密度と電界をセットで計測する必要があった。
そこで研究グループは、サイコロの5の目配置を採用した独自の電極構成により再現性の高い単一フィラメントのストリーマ放電を生成した。このストリーマ放電に対し2波長Talbot干渉計を適用することで、電子密度の2次元分布をシングルショットで可視化し、さらに電界誘起第2高調波発生(E-FISH)法では電界ベクトルの1次元分布を測定した。
まず、電子密度と電界の実測結果が互いに整合していることを電子に対する連続の式を解くことで実証した。次に、既存の理論・数値計算モデルによって得られた予測結果の妥当性を吟味することで、これらの従来研究では実験結果が正確に再現できていないことを明らかにした。
さらに、この原因は1次から2次への遷移過程において、陰極近傍で生じる高電界領域の広がりによるものであることを明らかにした。
この成果は既存モデルの妥当性を検証し、既存モデルの改良・精緻化に供する初めての実験的ベンチマーク。こうした総合的な検討を通して最後に、2次ストリーマ放電の普遍的な支配機構は電流の連続性であることを示した。
研究グループは、放電の予測・制御性能向上により、雷現象の理解や放電の医療・農業・環境・エネルギー応用が加速するものと期待されるとしている。