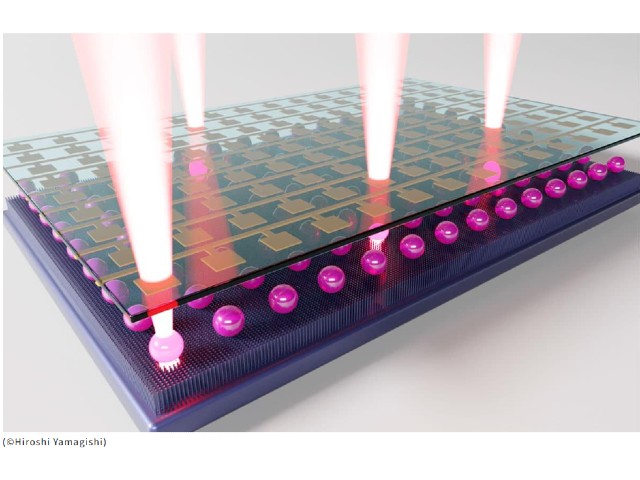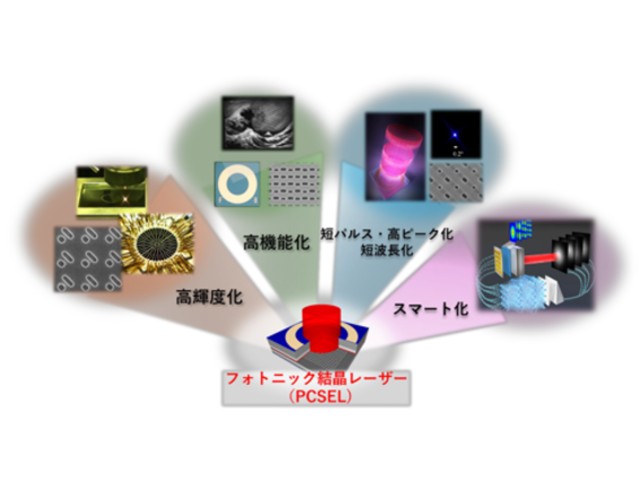高知工科大学と筑波大学は,設計したtBuCという分子の結晶自身が高い発光性を持つ共振器構造として機能し,単結晶レーザー機能を発現させることに成功した(ニュースリリース)。
化学構造のデザインによって容易に波長を制御できる新規性のある光源として,有機レーザーが注目されている。これらの媒質として,ある程度高い固体発光性を示すCDSBの誘導体が関心を集めていた。
しかし,これらは溶解性に乏しく,レーザー機能発現に至るほどには発光性がなく,有機単結晶レーザーを実現するためには,溶解性を向上させることによって溶液法での結晶化を容易にし,共振器構造を備えた有機単結晶を作製する必要があった。
研究グループは,CDSB分子の両端にtBu基を導入した新規化合物,tBuCを合成したところ,室温下でのクロロホルムへの溶解度が10倍以上高まった。この高い溶解性を活かし,室温下にて様々な濃度で結晶作製を行なうと,緑色蛍光を示す板状結晶(I型)と青色蛍光を示す針状結晶(II型)の2種類の結晶を見出した。発光性を評価する指標の一つである蛍光量子収率(ΦPL)を算出すると,I型では0.72,II型では0.91だった。
II型結晶は,特に蛍光性に優れ,CDSB系分子の中で最高値のΦPLを示した。結晶構造を見ると,tBu基のかさ高さが分子同士の密な集積を妨げており,その結果として高いΦPLが発現しているものと解釈できた。
II型結晶は,高い蛍光量子収率を示していた上,レーザー発振に都合の良い1次元に伸びた結晶形状をしていたため,光励起による発光スペクトル測定を通してこの結晶のレーザー特性を調査した。すると,低い励起エネルギー密度ではなだらかな通常の蛍光スペクトルが見られたのに対し,励起エネルギー密度の上昇によって発光スペクトルの急激な強度増大と狭線化が見られた。
この高エネルギー励起下での発光スペクトルを高波長分解によってスペクトルを測定すると,等間隔に鋭さをもったパターンが表れており,結晶自身が光を効率よく閉じ込める共振器として機能していることを示していた。
レーザー発振下での結晶の蛍光像を見ると,結晶端2箇所から強く光を放射している様子が見られ,良質な結晶性が共振器機能を担保していると考えられる。これらの結果は,tBuCのII型結晶がレーザー機能を有することを表しているという。
研究グループは,様々な分子骨格にこのデザイン方法を適用することで,溶液法による高輝度デバイス作製に向けた広範な材料開発が期待できるとしている。