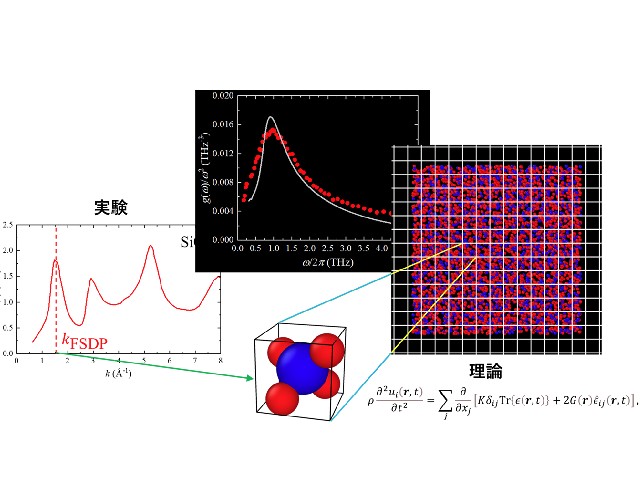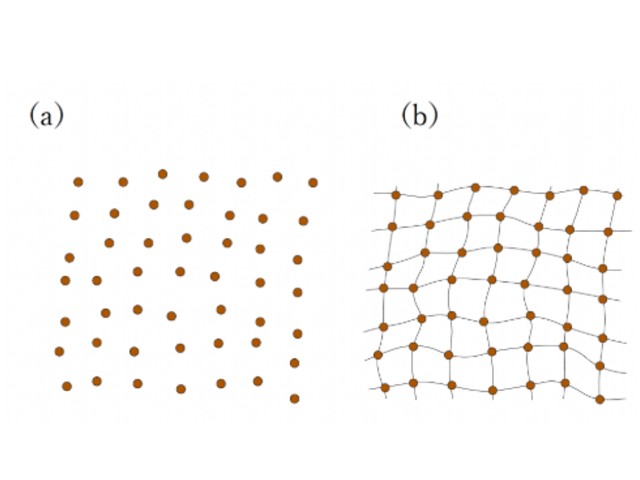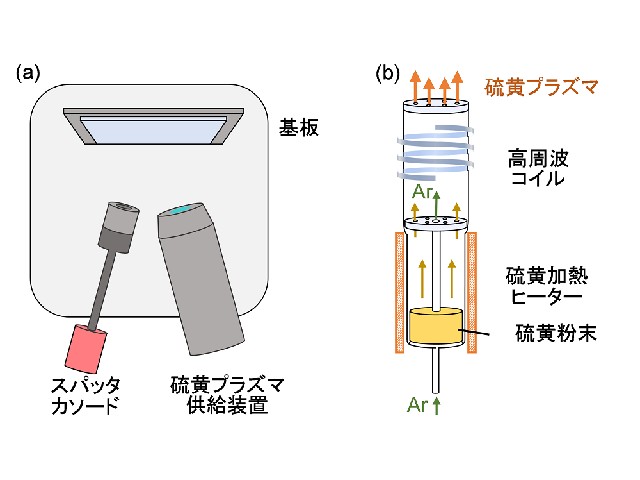京都工芸繊維大学は,タンパク質をもとにした物質を固定した,低温ガラス面上の水滴の凍結抑制について明らかにした(ニュースリリース)。
固体表面への氷の付着は,飛行機・鉄道・自動車・船舶の事故を引き起こし,送電線の断線やエアコン室外機の故障を生じさせる。この問題に対して加熱や除氷剤の使用がなされているが,エネルギー損失や環境破壊の問題を引き起こすため,氷の付着しにくい面の開発が活発に行なわれている。その多くは金属やプラスチックの加工面であり透明ではない。
そこで,研究グループは,寒い海に棲むある魚が持っている氷成長を抑制する不凍タンパク質をもとにした物質に注目した。この物質を表面に固定して凹凸がナノレベルの新しい機能表面を創製することにより,ガラス面に着いた水滴の凍結を抑制できると予想した。
具体的には,水の凍結抑制を評価する指標として,水滴の形状,凍結前の最低温度である過冷却温度,面に付着した氷を剥がすのに必要な付着力に焦点をあてて測定を行なった。水滴の形状と凍結の様子は,ビデオマイクロスコープにより観察した。水滴の温度は,細い熱電対を用いて測定した。付着力の測定には,モーターやロードセルを組み合わせて自作した付着氷を押す装置を用いた。
この実験の結果,作製した面上の水滴の過冷却温度は,無垢のガラス面の場合の過冷却温度より6℃以上低くなった。このとき0℃から過冷却温度になるまでの時間は,ポリペプチドを固定した面の場合には無垢のガラス面の場合に比べておよそ100~300秒も長くなった(率にして25~67%)という。
今回の研究により,作製した機能表面により水の凍結が遅らされたことが明らかになった。また,作製した面に付着した氷の付着力は,無垢のガラス面の場合の付着力より20%以上低い結果を得た。この研究により,作製した機能表面に付着した氷はより簡単に剥がすことができることが明らかになった。
金属板やプラスチック板を加工して氷の着きにくい面を開発した例はあるが,濡れやすく透明なガラス面の開発例は極めて少ない。研究グループは,今回の研究により,カーブミラー,あるいは自動車や鉄道車両の窓に氷が付着して引き起こされる交通障害を防ぐことや,太陽光発電パネルに氷が付着して発電効率が落ちることを防ぐことに貢献できるとしている。