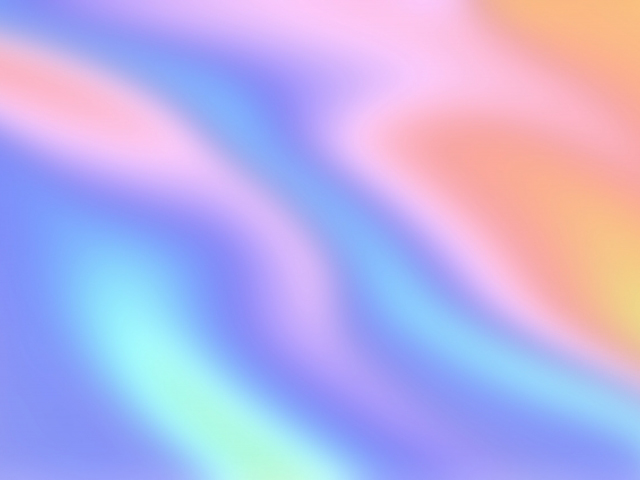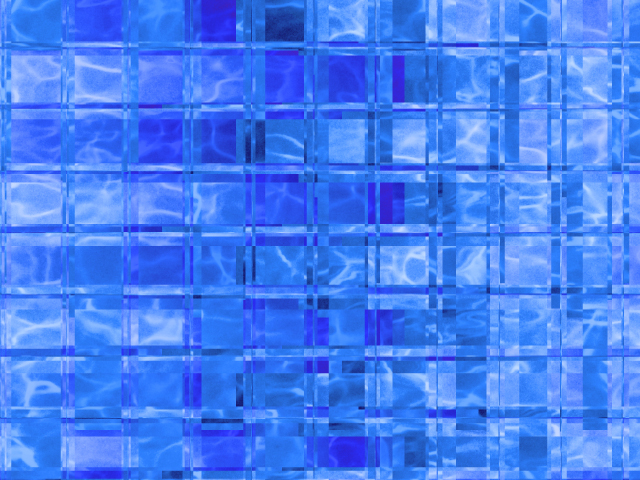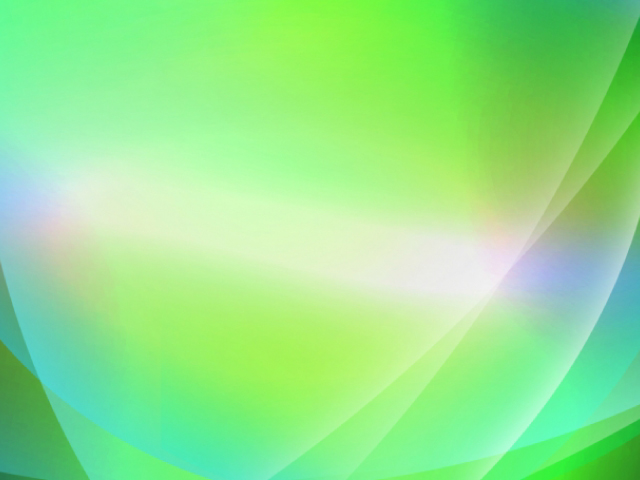4. まとめ
高配向性メソポーラスシリカ薄膜に金を斜め蒸着することで,十ナノメートルスケールの金メソグレーティング構造を作製する研究に関する途中経過を報告した。上述のとおり,まだデザインした構造を得るには至っておらず,構造制御には金属の薄膜上での拡散を抑えることが鍵となる。透過率測定の結果,マクロスコピックな光学応答は理想的なメソグレーティング構造により解釈可能であり,現状レベルの構造制御においても顕著な光学異方性の発現が見られた。
またシミュレーションの結果により,ロッド径とギャップ距離という,比較的簡単なパラメタの制御により幅広い波長選択性をもったプラズモニック構造の作製が可能であることが示唆された。構造制御の洗練により,波長板と偏光子の機能を併せ持つような薄膜の作製にまで進むことができれば応用にもつながると考えられる。今後,得られた構造が狙い通り高密度なナノギャップに由来する機能を発現するか,Raman散乱や発光増強効果などを検証していく予定である。
謝辞
ラビング処理基板をご提供くださいました宮田浩克様(キャノン㈱)に深謝いたします。
2)J. C. Hulteen and P. Van Duyne, J. Vac. Sci. Tech. A13, 1553 (1995)
3)Y. Sawai, et al., J. Am. Chem. Soc. 129, 1658 (2007)
4)M. Suzuki and Y. Taga, J. Appl. Phys. 90 5599 (2001)
5)K. Okamoto, B. Lin, K. Imazu, A. Yoshida, K. Toma, M. Toma, and K. Tamada, Plasmonics 8, 581 (2013)
6)T. Kondo, H. Masuda, and K. Nishio, J. Phys. Chem. C117, 2531 (2013)
7)M. Huth, K. A. Ritley, J. Oster, H. Dosch, and H. Adrian, Adv. Func. Mater. 12, 333 (2002)
8)T. Yanagisawa, T. Shimizu, K. Kuroda, and C. Kato, Bull. Chem. Soc. Jpn. 63, 988 (1990)
9)C. T. Kresge, M. E. Leonowicz, W. J. Roth, J. C. Vartuli, and J. S. Beck, Nature 359, 710 (1992)
10)G. Kawamura, I. Hayashi, H. Muto, and A. Matsuda, Scr. Mater. 66, 479 (2012)
11)M. Kobayashi, Y. Kanno, and K. Kuroda, Chem. Lett. 43, 846 (2014)
12)E. D. Palik, “Handbook of Optical Constants of Solids” (Academic Press, Boston, 1985)
13)S. Hayase, Y. Kanno, M, Watanabe, M. Takahashi, K. Kuroda, and H. Miyata, Langmuir 29, 7096 (2013)
14)S. Murai, S. Uno, R. Kamakura, K. Fujita, K. Tanaka, ECS Trans., 69 117 (2015).
■Department of Material Chemistry, Graduate school of Engineering, Kyoto University / PRESTO, JST
所属:京都大学 大学院工学研究科 材料化学専攻/JSTさきがけ
(月刊OPTRONICS 2016年8月号)
このコーナーの研究は技術移転を目指すものが中心で,実用化に向けた共同研究パートナーを求めています。掲載した研究に興味があり,執筆者とコンタクトを希望される方は編集部までご連絡ください。
また,このコーナーへの掲載を希望する研究をお持ちの若手研究者注)も随時募集しております。こちらもご連絡をお待ちしております。
月刊OPTRONICS編集部メールアドレス:editor@optronics.co.jp
注)若手研究者とは概ね40歳くらいまでを想定していますが,まずはお問い合わせください。