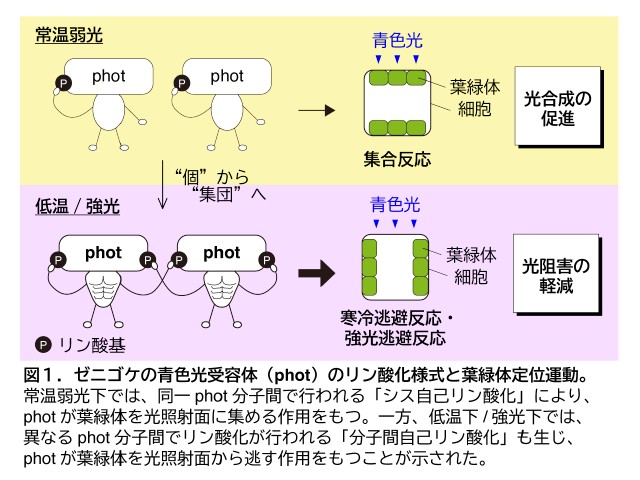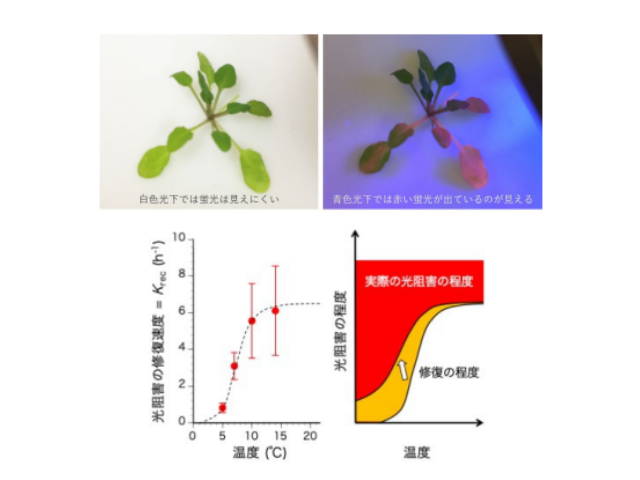名古屋大学の研究グループは,植物が適切なタイミングで花を咲かせ,それに合わせて花茎を伸ばす新規の機構を発見した(ニュースリリース)。
植物は常に季節の変化を感じながら,受粉そして結実に最適なタイミングで花を咲かせ,また開花に伴い茎を伸ばす。これは次世代を残す上で欠かせない役割を果たしているが,これまで野外で生育する植物が,適切な時期に開花と茎伸長を同調して促進させるメカニズムは不明だった。
研究グループは,季節変化の認識に重要な役割を果たすことが知られている篩部伴細胞に着目し,この細胞における特有の遺伝子発現パターンを解析した。その結果,開花が促進される長い日照条件によって,葉の篩部伴細胞でFPF1-LIKE PROTEIN 1(FLP1)という機能未知の遺伝子が強く発現することが分かった。
さらなる詳細な解析から,葉で発現したFLP1タンパク質が篩管を通って茎の先端部(茎頂)に移動し,開花と花茎伸長の両方を促進していることが示された。つまり植物は葉で感知した季節情報を,FLP1を介して茎頂に伝え,花芽の形成と茎の伸長を同時に促す巧みな機構を持っていることが明らかになった。
植物の開花のタイミングは野外に生育する植物の生存にとどまらず,作物の農業生産性,特に低緯度地域由来の多くの作物種の高緯度地域での栽培を可能にするために決定的な役割を果たす。例えば中国南部由来のジャポニカ米は,もともと日照時間が短くならないと出穂(稲の開花)しない植物だったが,日照条件に非感受な品種が作られ,北はシベリアの高緯度地域まで栽培することが可能になっている。
これまで開花の制御に関する研究は,FT遺伝子の発現制御やFTタンパク質の挙動を中心としたものだったが,研究グループは今回FLP1を発見したことで,この研究分野に新たな方向性が示されたとしている。また,FLP1が茎の伸長にも寄与していることから,野菜が花茎を伸ばすことで商品価値を毀損する「トウ立ち」を人為的に制御することで,優良な作物品種の作出にも繋がる可能性があるとしている。