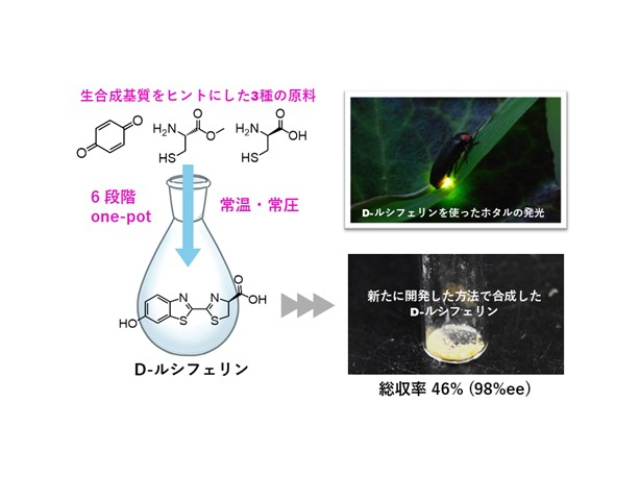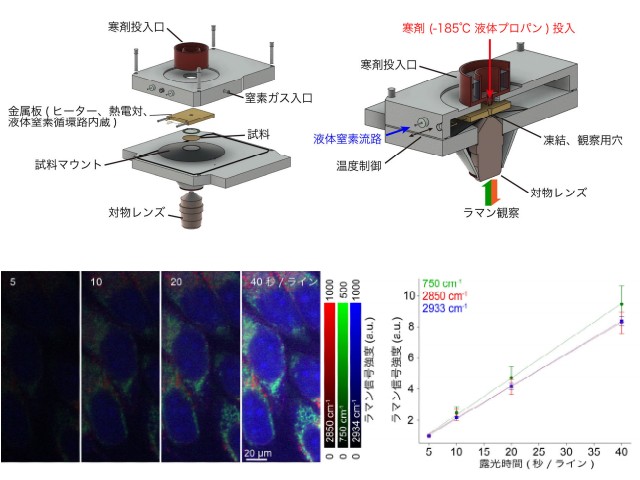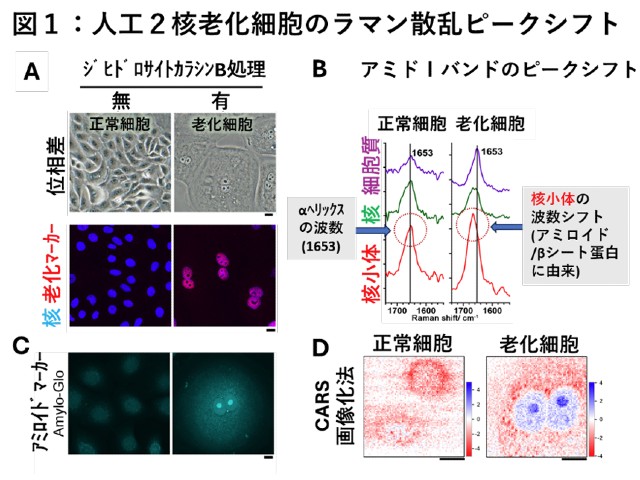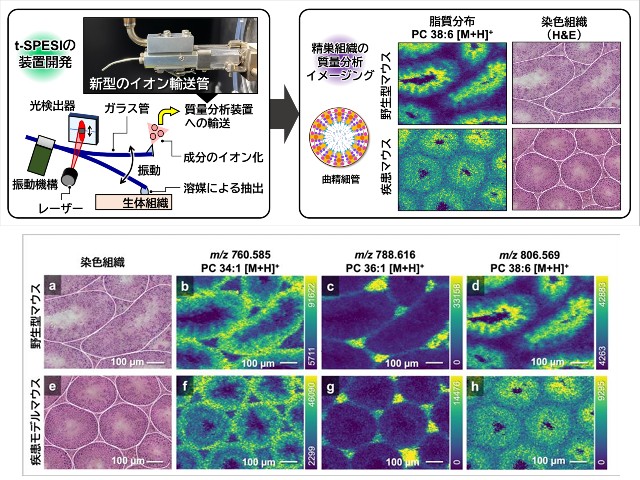大阪大学と慶應義塾大学は,生物発光の波長(色)を自在に変化させ,個々の細胞を標識することで,複数の細胞を同時に観察する新たな手法を確立した(ニュースリリース)。
細胞集団において個々の細胞を識別する方法は,細胞運命や薬剤応答など細胞の個性の違いが注目されている現在,その重要性が高まっている。生物発光を用いた細胞識別法の確立には,1. 生物発光の発光色を増やす方法,2. 多数の発光色を同時に検出する方法,の2点が課題となっていた。
研究グループは生物発光の発光色を増やすために,以前開発した生物発光タンパク質enhanced Nano-Lantern(eNL)を基盤にした。eNLは青色生物発光タンパク質NanoLucに蛍光タンパク質を繋げることで,生物発光エネルギー共鳴移動(BRET)を引き起こし,その発光色を変化させている。
今回,eNLにさらに蛍光タンパク質を繋げることで複数のBRETを誘導し,より複雑な発光色を作り出すことに成功した。最終的に20色にまで発光色のバリエーションを増やし,この生物発光タンパク質シリーズをeNLEX(eNL expansion)と名付けた。
光学フィルターを切り替えてモノクロカメラで検出する従来の方法では,20色のeNLEXの発光色を同時に観察することは不可能。そこで検出の手段として,スマートフォンなどに装備されているカラーCMOSカメラを用いた。
これらのカメラは,検出素子であるCMOSセンサー上にRGBを基本とするフィルターが並んでおり,観察対象から発せられる光を,フィルターを通して検出することで,発光の波長情報を記録することができる。
このカラーCMOSカメラを顕微鏡に設置して,細胞観察での実用性を検証した。eNLEXそれぞれをヒトの培養細胞へ導入して観察した結果,個々の細胞から発せられる20色の発光が同時に観察可能であることが示された。eNLEXとカラーCMOSカメラを組み合わせた撮影は,細胞以外にも細胞内小器官の識別から,小動物の組織レベルに至るまで,様々なスケールの観察対象に対して実行できる。
また,撮影した画像からRGB情報を基にそれぞれの発光色を分離することにも成功した。さらに生きた細胞内での複数の対象について,eNLEXでそれぞれ標識することでその経時的な変化を同時に観察することも可能であり,簡便なシステムでタイムラグのない観察を実現した。
研究グループは,細胞集団中のそれぞれの細胞を追跡することが容易になり,細胞運命の追跡や,薬剤応答に個性的な反応を示す細胞の探索など,様々な解析への応用が期待されるとしている。