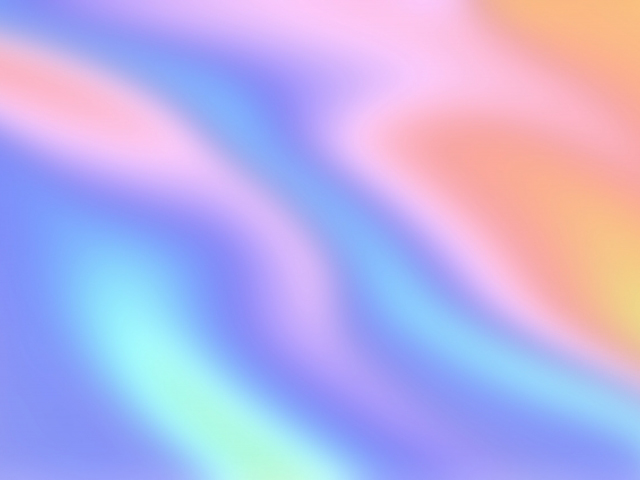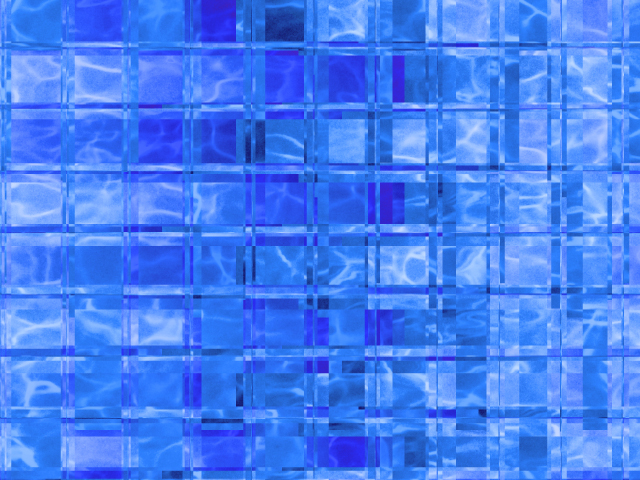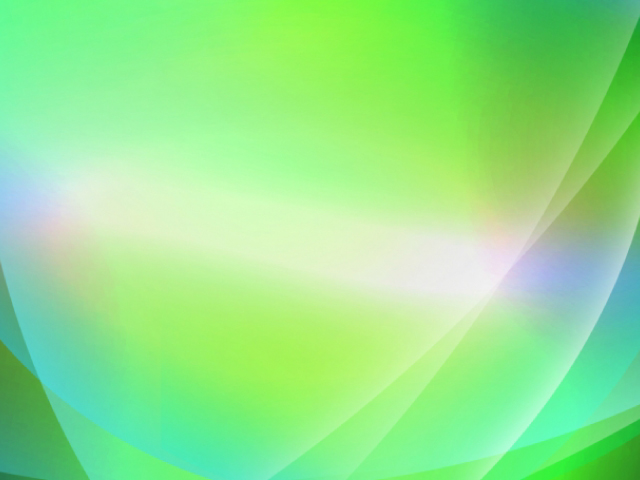ミニインタビュー
田嶌先生に聞く
これまでの考えを覆す計測技術を創り出す

─この研究を始めたきっかけを教えてください。
(田嶌)博士課程で,多くの粒子や光子を使って量子もつれを生成するという,量子情報分野に関する研究をしていたのが原点です。これは,量子情報処理の中核をなす基盤となるもので,それに関わる研究は常に意識してきました。中遠赤外領域は2000 nmを超える波長で,まだまだ未知の領域です。その中で,今回の赤外分光計測装置で活用できる研究というのは魅力的だと思いました。
─この研究の面白さを教えてください。
(田嶌)量子赤外分光では,赤外光の情報を可視領域で取得することができます。つまり,赤外光と異なり黒体輻射の影響を受けることがなく,吸収の情報が得られることになります。また,可視光は,高感度で非常に安い価格の検出器が使用できます。そのため,今までの量子赤外分光の考えを覆すような計測技術を作れるところが非常に面白いです。
─研究している中で苦労していることはありますか。
(田嶌)赤外波長2000 nm以上の今までの光学素子は,量子操作の観点からは精度の高いものが少なく,高性能なものを探して使ったり,我々自身で作ったりしていかなければなりません。特に今回の研究は,非常に広い帯域の光学素子が要求されたのですが,島津製作所と共同研究することで非常に精度の高い光学素子を作製できました。現在私は,情報通信機構とも連携し産官学により中赤外領域の“検出器”に関する研究にも取り組んでいます。計測技術の向上ははもちろんのこと,未踏領域を開拓すべく中赤外領域での量子情報研究を推進していけたらと考えています。
─この研究がどのように応用されることを期待していますか。
(田嶌)今回紹介した私が取り組んでいる研究の論文(参考文献4)は,2024年に出された論文(Physics)の中で被引用件数(他の研究等で引用された件数)が,TOP1%と非常に高い関心が寄せせられています。最初は使用できる分野が限られかもしれませんが,将来的には,医療や環境など様々な分野で身近に使用される技術として発展することを期待しています。また,従来の赤外分光では評価が難しい,もしくは,今まで検出されていない情報が得られる可能性も非常に高いと思っています。
─若手研究者が置かれている状況をどう見ていますか。
(田嶌)将来が期待されるような新しい基礎研究の予算は,少なくなってきていると感じています。若い世代が技術を創ることは,次世代にとっても大事なことだと思いますので,基礎研究の強化と支援は願って止まないところです。
─さらに若手や学生に向けてメッセージをお願いします。
(田嶌)量子赤外分光はまだまだ課題が山積みの分野です。新しい人が入って,新しいアイディアを持ち寄ってくれれば,研究の発展やスピードアップも期待されると思います。若い人にもこの分野に目を向けてもらい,一緒にやりませんかと呼びかけていきたいですね。
(聞き手:梅村舞香/杉島孝弘)
タシマ トシユキ
所属:京都大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 特定研究員
略歴:2009年3月 大阪大学大学院 基礎工学研究科 物質創成専攻 物性物理工学領域 博士後期課程修了(理学)。その後,大阪大学大学院 基礎工学研究科 GCOEプログラム特任助教(井元研究室),Ludwig-Maximilians-Universität München(Max Planck Institut für Quantenoptik) Prof. H. Weinfurter group 日本学術振興会 海外特別研究員,大阪大学大学院 基礎工学研究科 特任助教(鈴木研水落グループ),University of KwaZulu-Natal(南アフリカ共和国), school of chemistry and physics, Prof. M. Tame, group 博士研究員,2017年4月から京都大学大学院 工学研究科 特定研究員。
趣味:料理(ご飯からスイーツまでなんでも。テレビで気になったレシピに挑戦!)
(月刊OPTRONICS 2025年3月号)