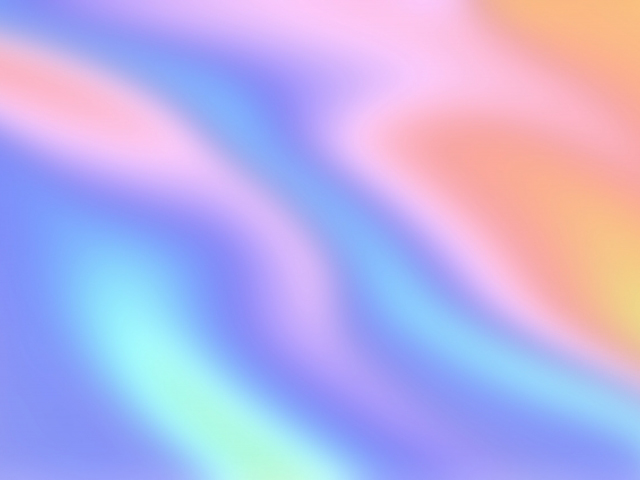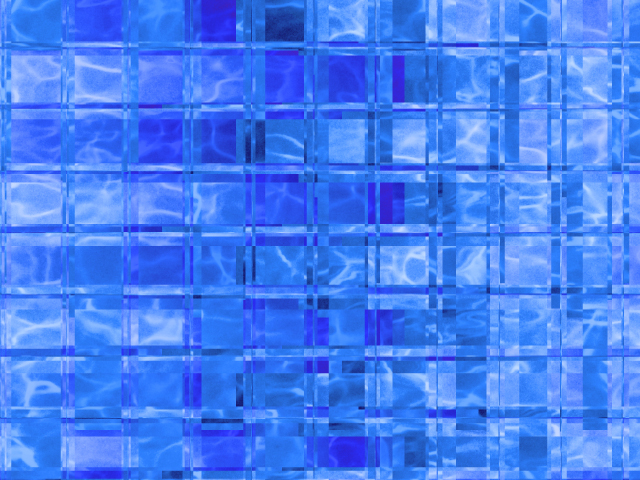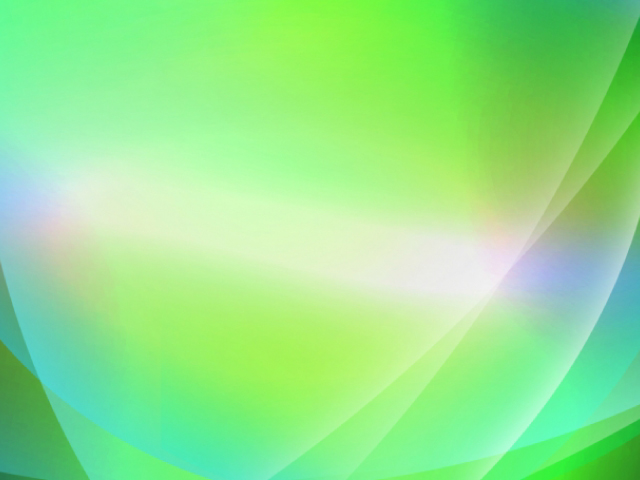6. おわりに
本研究成果は,我々の身近なもの,webカメラやスマートフォンなどで使用されているシリコン光検出器を活用し,2−5 μmの広い中赤外領域で高精度な吸収スペクトルを測定できることを示唆した。この技術は,従来の赤外分光装置に匹敵する性能を持ちながら,小型化と高感度化を大きく前進させる重要な成果である。将来的には,医療,セキュリティ,また,電池で動くコンパクトで高性能な赤外分光装置が実現できれば環境モニタリングなどのオンサイトでの測定など幅広い分野で活用されることが期待される。さらに,本研究で開発した超広帯域量子もつれ光源の技術は,量子通信や量子コンピューターなどの光量子情報処理の実現にも貢献することが期待される。
謝辞
本稿で紹介した研究成果は,研究室を主宰し本研究プロジェクトを率いる竹内繁樹教授,また,岡本亮准教授,向井佑助教,当時博士課程学生の荒畑雅也さん,修士課程学生の小田哲秀さんと協力することで得られたものであり,深く感謝いたします。また,共同研究者の島津製作所の徳田勝彦主任研究員,久光守主任により,本研究の要であるチャープ型擬似位相整合素子を作製して頂いたこと,深く感謝いたします。これらの研究は文部科学省Q-LEAP プロジェクト(JPMXS0118067634),内閣府官民研究開発投資プログラム(PRISM),科学研究費(26220712, H1702936)の支援を受けました。ご支援に感謝申し上げます。
参考文献
1)竹内繁樹:日本物理学会誌, 69 (12), 852-859 (2014).
2)竹内繁樹,岡本亮,田嶌俊之,向井佑,曹博:光学, 49 (8), 317-323 (2020).
3)G. B. Lemos, V. Borish, G. D. Cole, S. Ramelow, R. Lapkiewicz and A. Zeilinger, Nature 512, 409-412 (2014).
4)T. Tashima, Y. Mukai, M. Arahata, N. Oda, M. Hisamitsu, K. Tokuda, R. Okamoto, and S. Takeuchi, Optica 11, 81-87 (2024).
5)D. A. Kalashnikov, A. V. Paterova, S. P. Kulik, and L. A. Krivitsky, Nat. Photonics 10 (2), 98-101 (2016).
6)Y. Mukai, M. Arahata, T. Tashima, R. Okamoto, and S. Takeuchi, Phys. Rev. Appl. 15 (3), 034019 (2021).
7)M. Arahata, Y. Mukai, B. Cao, T. Tashima, R. Okamoto, and S. Takeuchi, J. Opt. Soc. Am. B 38 (6), 1934-1941 (2021).
8)M. Arahata, Y. Mukai, T. Tashima, R. Okamoto, and S. Takeuchi, Phys. Rev. Appl. 18 (3), 034015 (2022).
9)Y. Mukai, R. Okamoto, and S. Takeuchi, Opt. Express 30 (13), 22624-22636 (2022).
10)J. Kaur, Y. Mukai, R. Okamoto, and S. Takeuchi, Phys. Rev. Appl. 22(4), 044015 (2024).
11)T. Kurita, Y. Mukai, R. Okamoto, M. Arahata, T. Tashima, H. Ota, K. Tokuda, and S. Takeuchi, Phys. Rev. Appl. 23(1) 014061 (2025).
12)A. Vanselow, P. Kaufmann, H. M. Chrzanowski, and S. Ramelow, Opt. Lett. 44, 4
■Quantum infrared spectroscopy with the ultra-wide mid-infrared region
■Toshiyuki Tashima
■Kyoto University, Department of Electronic Science and Engineering, Post-Doctoral Fellow