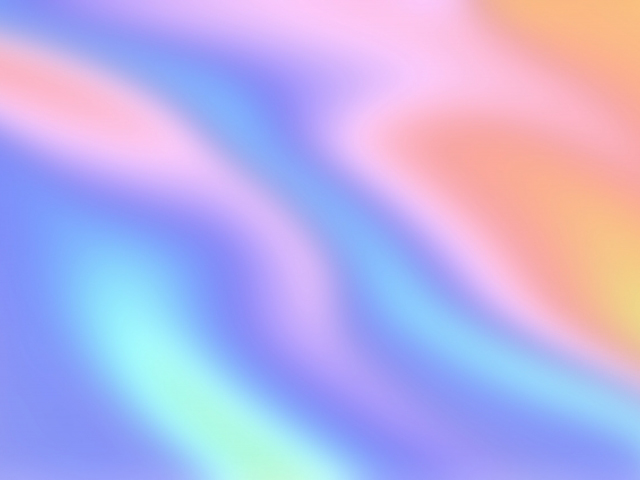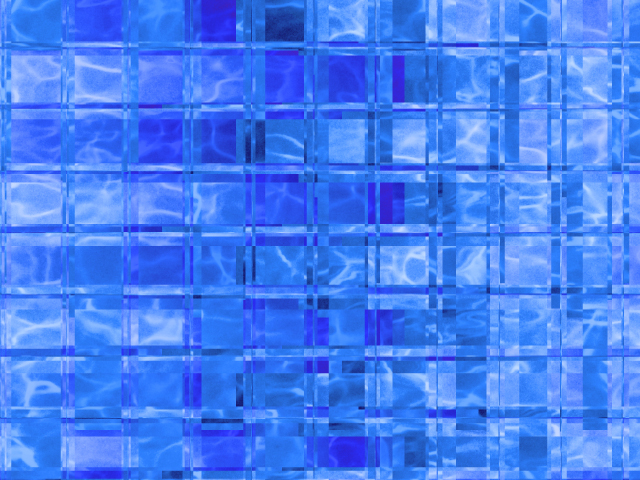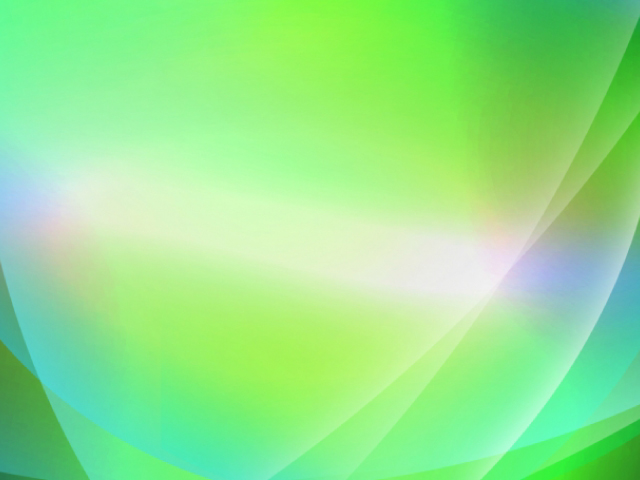しかしながら,これまでの研究においては,“量子もつれ光の帯域が赤外域で狭い範囲(1 μm以下)に制限”されていたことで,従来の赤外分光のような広い帯域幅での測定が困難であった8, 12)。例えば,フンボルト大学ベルリンのラメロー博士等のグループは,CH4ガス測定を帯域幅0.8 μmで実証しているが12),1 μm以下であった。
我々のグループでは,光子対の波長(帯域幅が4 nm程度)を変化させ掃引する手法により,赤外光子波長が2−5 μmの波長域の広帯域量子赤外分光を実証した8)。この研究では,高速の波長掃引分光法であるCoarse scan法を提案,実証している。測定を行いたいスペクトル構造に対して,量子干渉信号のピーク近傍の明瞭度変化のみを比較し一波長での測定必要点数を抑えることで広帯域の波長掃引分光測定を短時間に完了することができる。しかしながら,この手法では,「広帯域」と「高分解能」を両立するのが困難という課題があった。
最近,我々は,波長2−5 μmという広い波長域で中赤外光子を発生する超広帯域量子もつれ光源を開発して,それを用いた量子赤外分光に世界で初めて成功した3)。次節からは,その最新の研究成果について述べる。最初に,超広帯域量子赤外分光の核となる可視中赤外量子もつれ光源について説明する。次に,この光源を用いた超広帯域可視−中赤外量子赤外分光システムを説明する。最後に,このシステムを用いて実証した様々な無機・有機物の透過率評価の結果を紹介する。
3. 超広帯域可視−中赤外量子もつれ光源
量子赤外分光では,エネルギーが大きく異なる可視光子と赤外光子を持つ周波数もつれ光子対を利用する。このもつれ光子対は,非線形光学結晶を用いたSPDC過程により,ポンプ光子がエネルギーの低い2つの光子(シグナル光子とアイドラー光子)に分割され,エネルギー保存則により,ポンプ光子の周波数ωp,シグナルとアイドラー光子の周波数(ωsとωi)の間に,常に次の関係が成り立つ:ωp=ωs+ωi。ここで,ポンプ光の線幅が十分に狭い場合,シグナル光子とアイドラー光子の周波数の和は常に一定となる。生成される光子対の周波数の組み合わせは,このエネルギー保存則とSPDCにおける位相整合条件に依存する。

適切な非線形光学結晶の設計やポンプ光波長の調整を行うことで,光子対を特定の波長域で生成することが可能である。このようにして,一方の光子(シグナル光子)を可視光の波長域に,もう一方(アイドラー光子)を赤外波長域に発生させることができる。
中赤外域において広い周波数帯域で量子もつれ光を生成可能な「チャープ型擬似位相整合素子」を,島津製作所との共同研究により独自に開発した。今回,開発したチャープ型擬似位相整合素子の概念図を図2(a)に示す。
この素子は,周期的に分極が反転した構造を持つ擬似位相整合素子を基盤とする。分極反転周期によって,素子から生成される量子もつれ光の光子対の波長は決定されるため,分極反転周期を段階的に変化させる(チャープする)ことで,広い帯域にわたる量子もつれ光子対を生成することが可能となる。
図2(b)は,島津製作所と共同で作製したチャープ型擬似位相整合素子の光学写真である。チャープ型擬似位相整合構造を設計・製造するにあたり,マグネシウム添加定比タンタル酸リチウム(MgSLT)という材料を用いた。この作製した素子に励起レーザー光(ポンプ光)を入射し,SPDC過程により可視光子と赤外光子の対からなる広帯域量子もつれ光子対を発生させることができる。