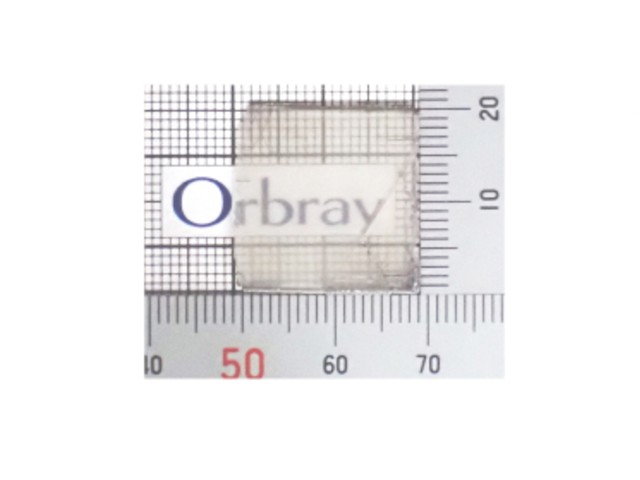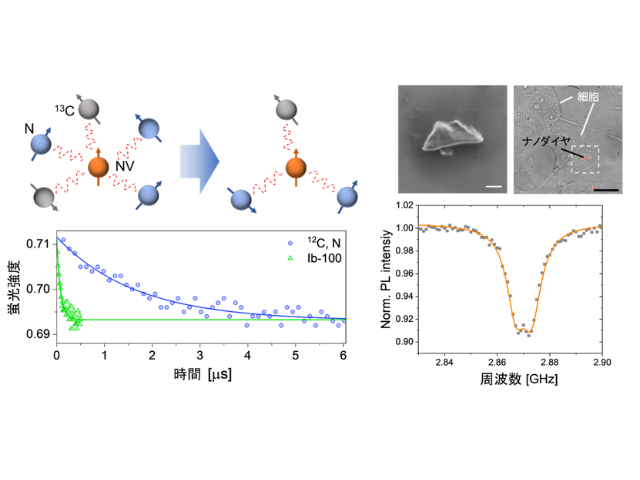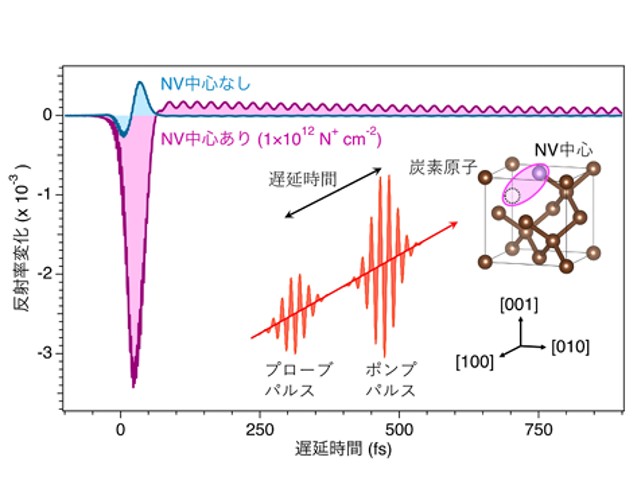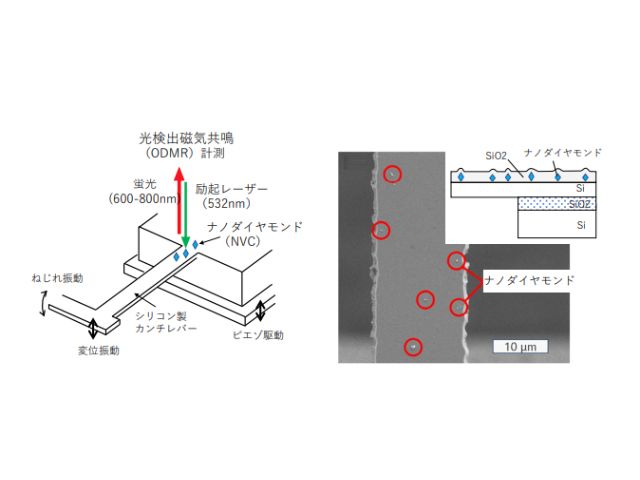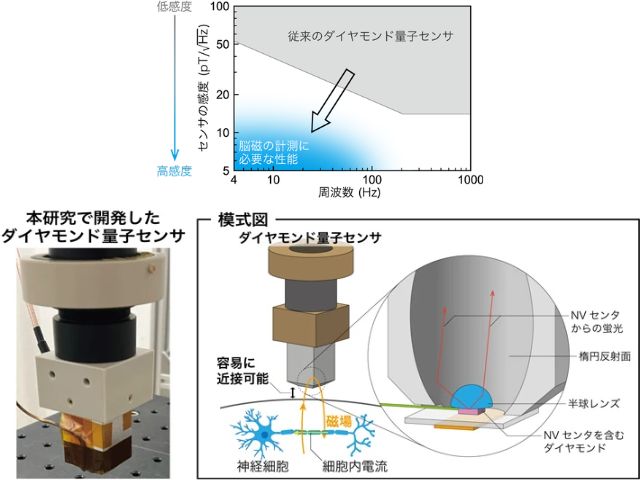ダイヤモンドは宝石として最高峰にあるが,科学分野においても重要な物質で,様々な応用がされている。例えば量子分野では,ダイヤモンド中に形成される窒素(N)と空孔(V)からなる格子欠陥「NVセンター」を,個体量子センサーや量子コンピューターへ応用する研究がされている。また,その優れた物性から,ヒートシンクや半導体材料,そして光学部品など,応用分野は多岐にわたる。

そうした応用のうち,地球の中心部に相当するような「高温・高圧」状態を再現する研究に用いられるのが,地上随一のダイヤモンドの硬さと,高い透明度を利用した「ダイヤモンドアンビルセル」だ。この装置は非常にシンプルで,宝飾用とよく似たカットを施された専用のダイヤモンドを2つ用意し,凸部分同士を突き合わせる形で器具にセットする。
ダイヤモンドの先端はわずかに平らになるように加工されており,ここに試料を挟み込み,人力で六角レンチでネジを締め上げ圧力をかける。また,ここにレーザーを照射すれば,レーザーはダイヤモンドを素通りして試料に当たるため,資料の加熱も同時にできる。こうして地球深部の圧力と温度(200GPa,4,000℃)を再現し,さらに光学的な観察も行なえるというものだ。
科学や産業では人工ダイヤモンドを用いることも多いが,ダイヤモンドアンビルセルではレーザーを通すため,透明度が重要なほか,機械的な破壊を免れるために傷や歪もご法度となる。また,安定的に圧力をかけるためには,加工の寸法精度や研磨精度も重要。そのため,ダイヤモンドアンビルセルには宝飾用の質の高いダイヤモンドが用いられることも多く,宝飾と科学という全く異なる領域ながらも,バイヤーの目利きが重要だというのは面白い。
以前取材した東工大講師で地球惑星科学を専攻する太田健二氏(現東京科学大准教授)の研究室では0.2カラットのダイヤモンドを使っていたが,実験中に割れてしまうこともあり,その価格に頭を悩ませているとの話しだった。現在,半導体材料としての需要もあり,人工ダイヤモンド基板は大型化が進む。これにより,近い将来,ダイヤモンアンビルセル向けの人工ダイヤモンドも質の向上と価格の低下が実現すれば,地球の生い立ちに新たなページが加わるかもしれない。【デジタルメディア編集長 杉島孝弘】