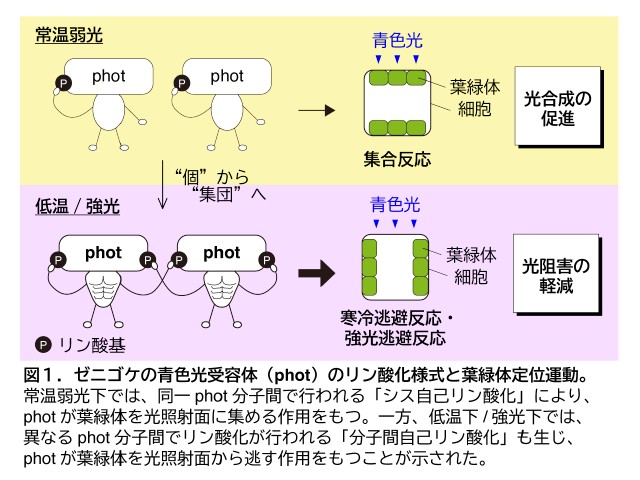沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究グループは,一部のバクテリアは,光合成によって酸素を生成する能力を獲得するよりもずっと以前から,微量の酸素を利用していた可能性があることが示唆されたと発表した(ニュースリリース)。
研究グループは,約23億年前に起こった「大酸化イベント(GOE)」において,微生物がどのように進化的に対応したのかを明らかにすることを目的とした。GOEは,シアノバクテリアによる酸素発生型光合成と,それに伴う炭素の堆積により,酸素のほとんどなかった原始地球の大気を,酸素の豊富な環境へと一変させた重要な地球規模の変化となっている。
これまで,このGOEの前後におけるバクテリアの進化の正確な時間軸を特定することは,化石記録の不完全さや古代微生物の年代測定の困難さから,非常に難しい課題とされてきた。特に地球形成初期の45億年前以降の空白期間は,従来の手法では扱いが困難だった。
そこで研究グループは,地質学的記録とゲノム情報を統合し,ベイズ統計を用いた革新的な進化年代推定モデルを構築した。大酸化イベントを時間的な基準とし,それ以前に好気性(酸素利用)細菌が存在していたかを,遺伝子構成と機械学習に基づいて予測した。特に,酸素を使った代謝の可能性を過去の遺伝子構成から逆算することで,当時の代謝様式を推定した。
その結果,少なくとも3つの細菌系統が,GOEより前,最も古いもので約9億年前にすでに酸素を利用する能力を持っていたことが判明した。これは,大気中に酸素が大量に存在する以前から,生命体が微量の酸素を利用していたことを示す発見となっている。
さらに,酸素を発生する光合成を行うシアノバクテリアの祖先で最も早期に好気性代謝が現れていた可能性が高いことも示唆されたという。
研究グループは,このことから,微量の酸素を使う能力が,やがて酸素を生成する光合成遺伝子の進化を促進した可能性があるとしている。