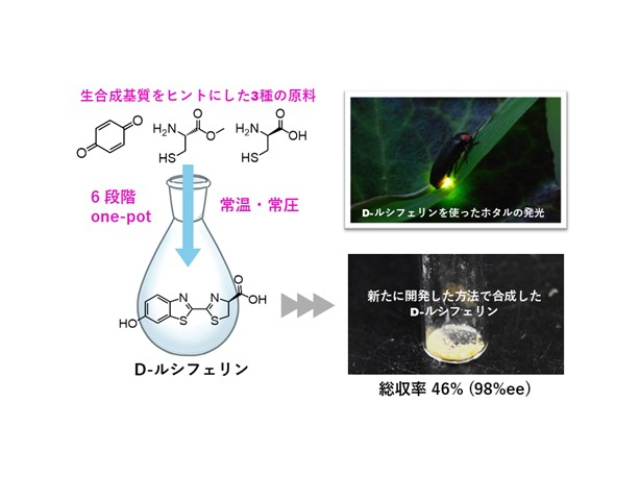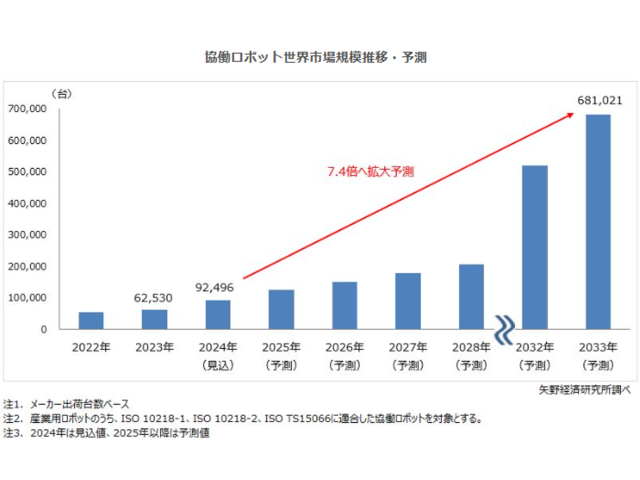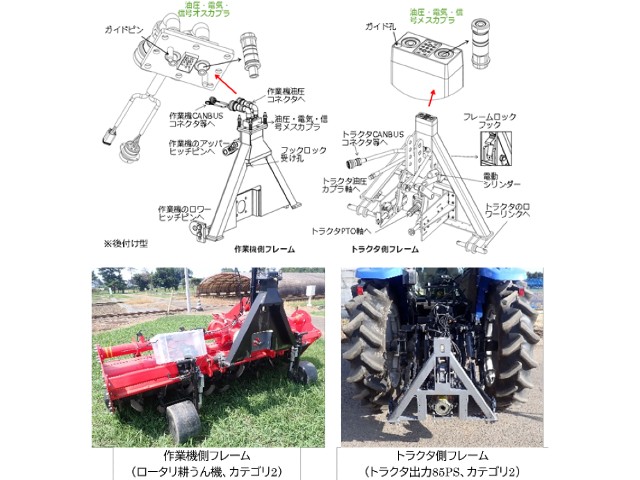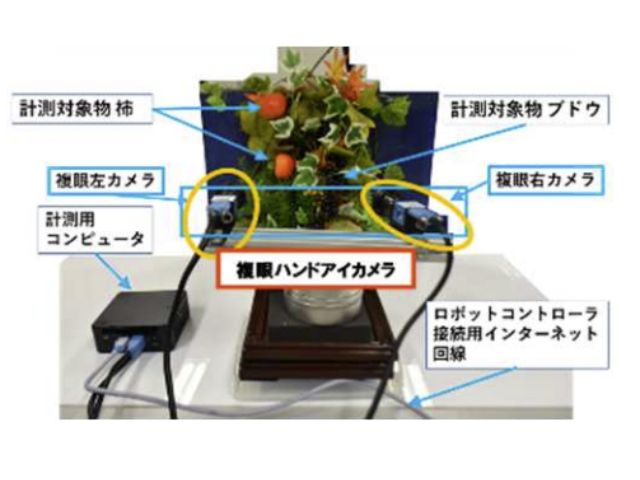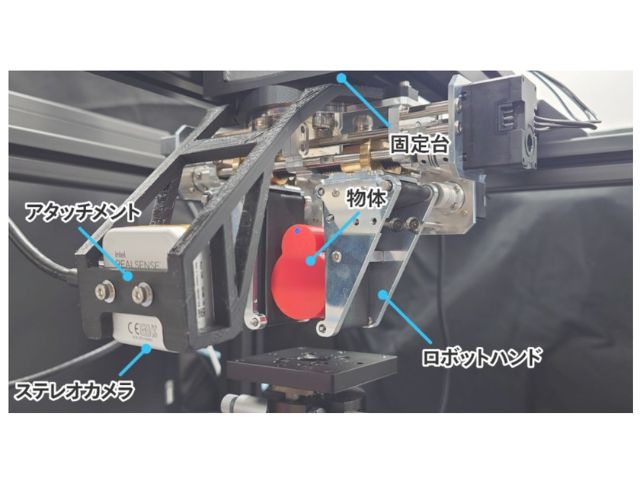電気通信大学,杏林大学,国立がん研究センターは,ソフトロボティクスにおける新たな発光機能として,生物由来の発光蛋白ルシフェラーゼを利用した生物発光の導入方法を確立した(ニュースリリース)。
ソフトロボティクスは,柔らかい材料でロボットを構成しようとする,近年注目されている分野。ソフトロボットには,その柔軟性と環境適応性から,自然環境における調査,災害救助,医療などを目的とした用途が見込まれている。
ソフトロボットの機能の一つである発光は,情報伝達や環境認識に重要。しかし,従来の電気発光(エレクトロルミネセンス)や化学発光(ケミルミネセンス)は人工的に合成された,場合によっては毒性のある材料を使用し,バッテリーなどの外部電源を必要とするため,エネルギー効率や安全性,環境負荷の面で課題があった。
研究グループは,大阪大学が開発したウミホタルルシフェラーゼ由来の発光蛋白ナノランタンを,哺乳類培養細胞に培養液中で分泌させることにより,目で見える程強く光る生物発光液を大量生産することに成功した。この液体は生物由来であるため安全で環境に優しく,発光に際し電気を消費しないため高いエネルギー効率が期待される。
次に,生産した生物発光液体にアガロースゲルを添加することで固体化による形状維持を図り,さらにこの固体の機械・電気的特性の評価を行ない,ソフトロボティクスに適用可能な発光電極を開発した。そして,開発した発光電極を静電力で動作するアクチュエータとセンサに適用した。これらのデバイスは,従来通りのアクチュエーションやセンシングの動作に加えて,変形に対する発光変化も示し,安定的な動作を実証した。
さらに,静電アクチュエータを発展させて,防水処理を施したクラゲ型ロボットを開発した。このロボットは,電圧の印加によるアクチュエーションと発光電極の機能によって,実際のクラゲのように発光しながら暗闇を遊泳できることを実証した。
これらの成果により,生物発光を活用したソフトロボットの実現可能性が示され,エネルギー効率が高く,安全で環境に優しい新たなロボティクス技術への道を開くことができた。研究グループは,この研究で実証された生物発光を活用したソフトロボットは,今後さらに多様な応用へと広がることが期待されるとしている。