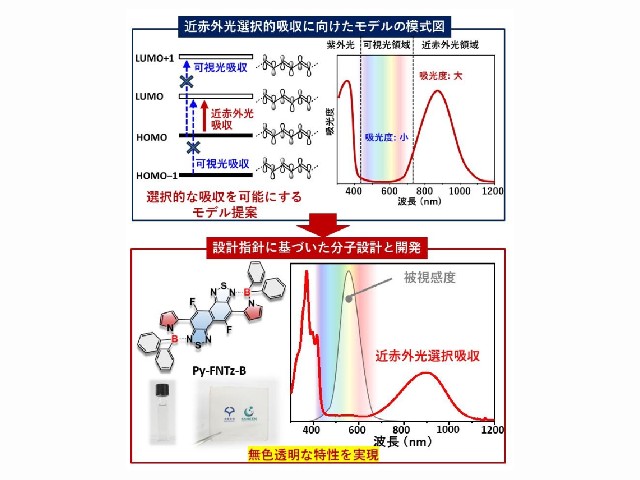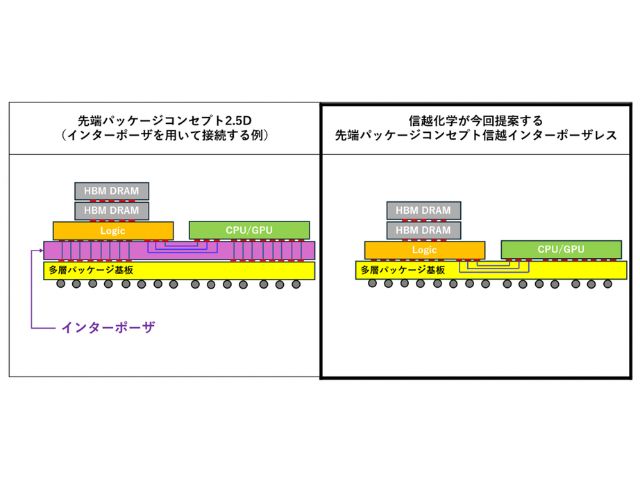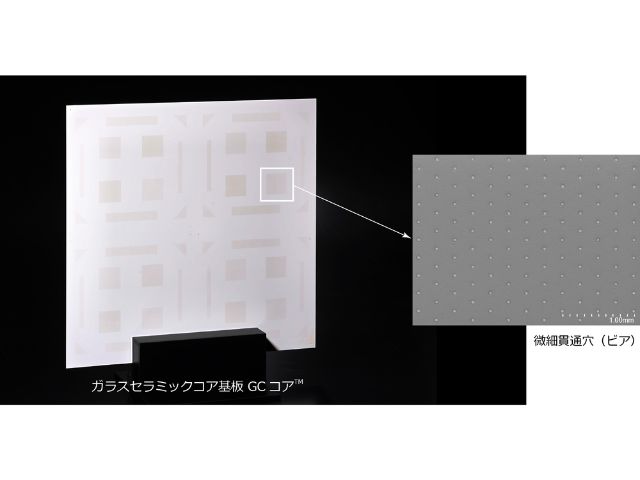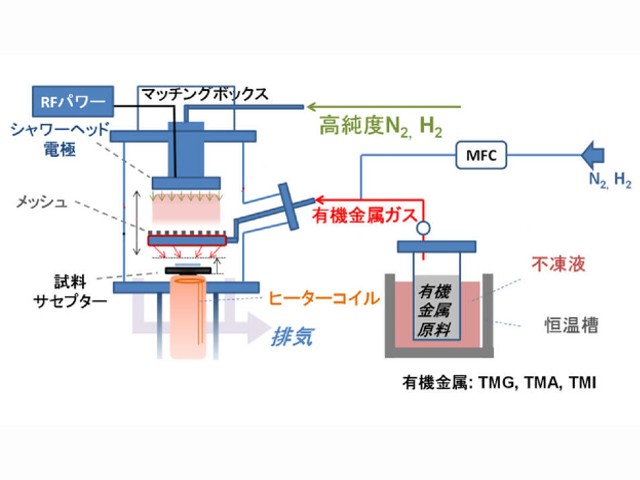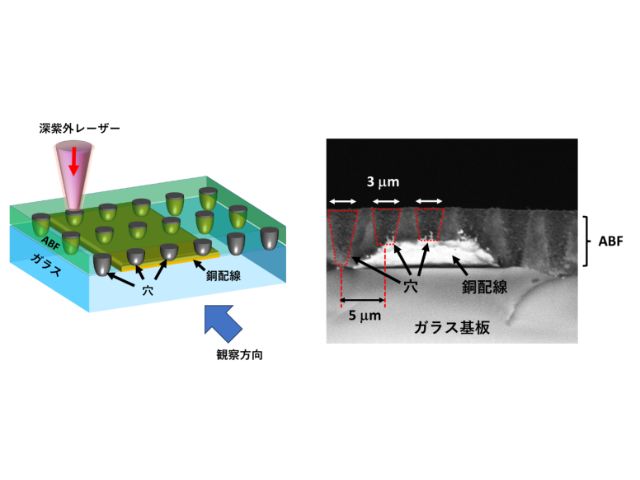京都大学と東京工業大学は,次世代半導体微細加工材料として注目されているポリスチレン(PS)とポリメタクリル酸メチル(PMMA)によるブロック共重合体であるPS-block-PMMAのつなぎ目にオリゴペプチドを精密に導入することで,PS-block-PMMAの相分離下限分子量よりも低い分子量で長周期のラメラ構造の形成に成功した(ニュースリリース)。
京都大学と東京工業大学は,次世代半導体微細加工材料として注目されているポリスチレン(PS)とポリメタクリル酸メチル(PMMA)によるブロック共重合体であるPS-block-PMMAのつなぎ目にオリゴペプチドを精密に導入することで,PS-block-PMMAの相分離下限分子量よりも低い分子量で長周期のラメラ構造の形成に成功した(ニュースリリース)。
混ざり合わない2種類の高分子をつなげたBCPは,同じ高分子同士が集まろうとして自己組織化を起こし,数十nmから数百nmの周期的規則構造を形成する。
このミクロ相分離と呼ばれる現象は2種類の高分子が混ざり合おうとしない反発力(偏析力)を表すχパラメーターと重合度(分子量)の積が,ある値以上にならないと起こらない。また,ミクロ相分離によって形成される規則構造の形態(ラメラ構造,円柱構造,球状構造など)は,両者のミクロドメインの体積分率によって決まり,規則構造の周期長は主に分子量によって決まる。
BCPを半導体材料として使う場合,基板に対する規則構造の配列配向制御,選択的な片成分除去,除去後の界面構造の粗さの低減など,様々な要件を満たす必要があることから,BCPの分子設計が鍵を握っている。とりわけ様々な特性バランスからPS-block-PMMAは最も有望なBCPの一つとして考えられている。
このPS-blockPMMAにおける大きな課題としてχパラメーターがそれほど大きくないために相分離させるためには高分子量体が必要であることが挙げられ,微細化を目指す上で低分子量体でも相分離させることが求められてきた。
ミクロ相分離は混ざり合わない高分子がお互いの界面をできるだけ減らすために起こる現象であり,相分離後に形成される界面にはBCPの「つなぎ目」が存在する。つなぎ目はBCPの分子全体から見るとマイナーな成分でありながら,BCPの相分離に大きな影響を与えると考えられ,これまでに両セグメントの界面に短いオリゴマーを導入して,低分子量PS-block-PMMAの相分離を促進する研究が報告されてきた。
今回研究グループは,アミノ酸6ユニットから成るオリゴペプチドをつなぎ目に導入することで,低分子量PS-block-PMMAの長周期ラメラ構造形成を実現した。その後の研究ではつなぎ目の構造が異なる10種類以上のPS-block-PMMAを系統的に合成し,つなぎ目の構造がほんのわずかに違うだけで,相分離挙動が変化することが分かっているという。
つなぎ目のオリゴペプチドの凝集とBCPの相分離が協調して自己組織化していると考えられ,研究グループでは半導体材料以外にBCPが用いられる材料(エラストマー材料,薬運搬材料,分散剤材料など)にも展開できるとしている。