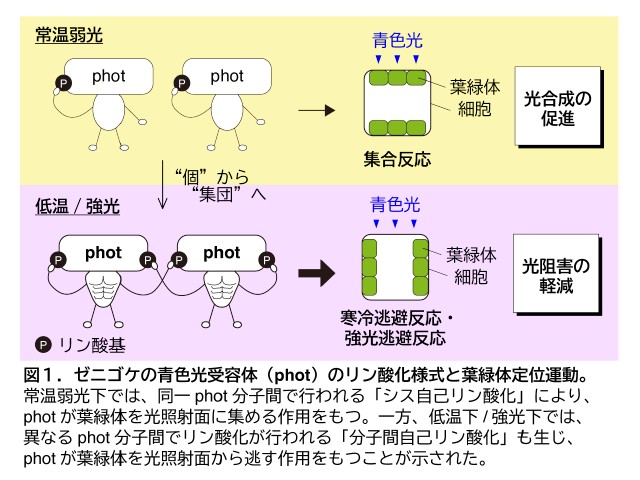帯広畜産大学を中心とする国際共同研究グループは,北海道・帯広におけるミツガシワの日中低下を発見した(ニュースリリース)。
帯広畜産大学を中心とする国際共同研究グループは,北海道・帯広におけるミツガシワの日中低下を発見した(ニュースリリース)。
光合成の日中低下(昼寝現象:midday depression)とは,晴天時の昼間に植物の光合成速度が低下する現象のこと。
これは,日中光が豊富にあるにも関わらず,二酸化炭素や水蒸気の出入り口である葉の気孔が葉が乾きすぎないように閉じたり,高温により酵素の働きが低下したり,強すぎる光によってダメージを受けたり,または,それらの組み合わせによって起こると考えられている。
日中に気孔を閉じる現象は,植物を支える土壌の水分状態に依存することが知られている。一般に,十分な降雨があった直後は日中低下が起こりにくく,逆に晴天が続いて土壌が乾燥すると日中低下が起こりやすいと考えられている。
そこで,土壌が常に水で満たされている抽水植物(根は水中にあり,葉は空中にある植物)では日中低下は起きないのかという議論について,先行研究では意見が分かれている。ヨシやマコモでは日中低下は起きないという報告がある一方,イネは日中低下を起こすという報告がある。
研究グループは,記録的な猛暑日であった2021年7月19日(地表25cm(葉の高さ)の最高気温37.9℃)と,あまり暑くなかった7月22日(気温29℃)において,帯広畜産大学ビオトープ(柏陵池)に生育している抽水植物ミツガシワの日中低下を調べた。
その結果,猛暑日では日中に気孔が閉じて光合成速度が低下する日中低下が観察され,これが葉の日合計の光合成量を17%減少させていた。一方,暑くなかった日には日中低下は見られなかったという。
この結果には二つの意味があるという。一つ目が,抽水植物では日中低下が起きる・起きないという明確な線引きがあるわけではなく,それは程度の問題のため,暑さなどが限度を超えた場合には抽水植物でも日中低下は起こるという点。二つ目は,一般に冷涼と言われている北海道の十勝・帯広であっても,猛暑日には植物の生産力が低下していたという点。
研究グループは,将来,気候変動により地球温暖化が進めば,これまで日中低下が起きにくいとされていた冷涼な北海道の植物も光合成の低下が起こることが懸念されるとしている。