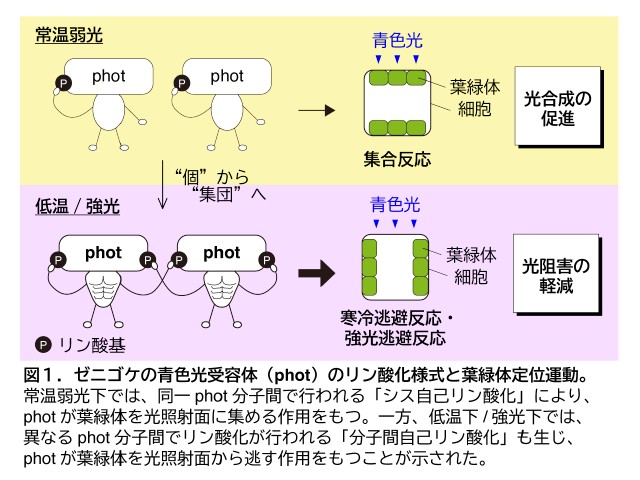東京大学と東北大学らの研究グループは,光が弱まると水草が減少し植物プランクトンが増加して,水質や生態系に大きな影響を及ぼすことを発見した(ニュースリリース)。
東京大学と東北大学らの研究グループは,光が弱まると水草が減少し植物プランクトンが増加して,水質や生態系に大きな影響を及ぼすことを発見した(ニュースリリース)。
現在,さまざまな人間活動によって,淡水生態系に降り注ぐ光の量は変化してきている。例えば,排水など濁った水が流入したり,池の上にソーラーパネルを並べたりすることで,池の光環境は大きく変化する。しかし,これまで湖沼生態系全体に及ぼす光量変化の影響は調べられてこなかった。
研究グループは,米コーネル大学が所有している30m四方,深さ1.5mの野外実験池において,プール用の遮光カバーを浮かべて太陽光を遮り,7月から3ヶ月間,生態系の反応を観測した。
その結果,暗い池ほど植物プランクトンが増加するという傾向が見られた。これは,光が減れば光合成速度が遅くなり,植物プランクトンが減少するだろうという当初の予想に反するもの。さらに,暗い池では植物プランクトンが増える一方で,湖底に生える水草(主にシャジクモ)が減る傾向があった。
このような複雑な観測結果を理解するため,光と栄養塩を巡って,水中の植物プランクトンと湖底の水草が競争するというシミュレーションを行なった。その結果,水中に差し込む光の量が減ると湖底まで届く光が少なくなり,水草が大きな打撃を受けて減少する一方で,水中の栄養塩が得られやすくなって,植物プランクトンが増えるという説明が可能であることがわかった。
ただし,遮光をしていない池では,上記の傾向に一致する,植物プランクトンが少なく水草が多い池と,植物プランクトンが多く水草が少ない池に分かれる結果になった。そこで,光が豊富な池での一般的な傾向を調べるため,遮光実験を行なわなかった35個の実験池で観測を行なった。その結果,水草の量が多い池と少ない池に二分化する傾向があることがわかった。
シミュレーションにおいても,光が弱い時は植物プランクトンが,光が強い時は水草が優先し,中程度の光の強さでは代替安定状態が生じて,水草が多く植物プランクトンが少ない池と,水草が少なく植物プランクトンが多い池に二分化する可能性が示唆された。
この成果は,光の変化に対して生態系がどのように反応するか,という問題の重要な一面を新たに発見したものであり,国内外の環境政策に影響する学術的知見として利用されることが期待されるもの。
また,社会の身近な問題である有害な藻類の大発生や水上太陽光発電の現場において,生物間相互作用の考慮を一層強く求めることにもつながることが期待されるとしている。