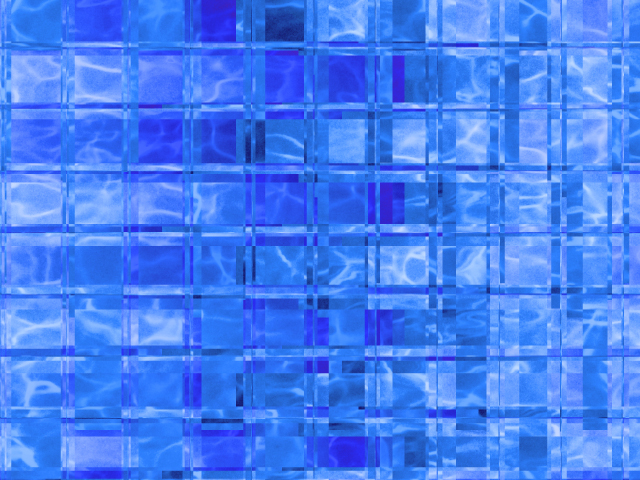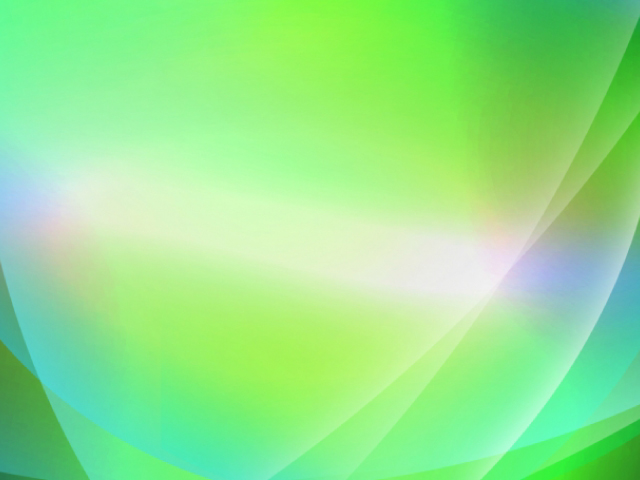1. 医療分野へのIoT導入

IoT(Internet of Things)とは,モノ同士がインターネットを介して接続され,お互いに通信しあい情報を共有し,制御しあう概念である。1999年にIoTが提唱され,約20年になり,それが現実のものとなる時代を迎えつつある。とりわけ2018,19年はIoT本格化の過渡期ともいえる年である。今後,IoTは更に発展し,2022年~2025年には年間約1兆個のセンサが出荷される。結果として,更に多種多様なセンサに囲まれた社会が構築され,より多くのセンサの種類と感度が社会から求められる。
現在,ヘルスケア,スポーツ,インフラストラクチャ,ロボティクス等多くの分野でIoTの普及が進めれている。その中でも,ヘルスケア・医療におけるIoTの普及は,社会保障費の過度な増大が問題となっている日本で最も注目されている分野の一つである。医療におけるIoTの導入はAI(人工知能),機械学習を基礎とした情報からのアプローチと,ウェアラブル端末を用いた機械電子(ハード)からのアプローチがあるが,両者は独立しているものではなく,相互に綿密に関係している。現在,ヘルスケア機器大手のオムロン社,ベンチャー企業のPGVなどでは遠隔治療に関するスマートデバイス,睡眠時の脳機能解析のためのウェアラブル型脳波計などについて研究・開発がなされている。一方で,医療用IoT研究として未開拓な分野がある。それがNICU(Neonatal Intensive Care Unit)を含めた新生児周産期医療である。
2. 新生児黄疸
新生児は出産とともに,母体に依存した胎内環境から,自らの力で生存する必要がある胎外環境への適応を迫られる。その変化は極めて大きく,様々な事象により,その生命は容易に脅かされる。また,自ら症状を訴えることができないため,対応が遅れることも珍しくない。そのため,持続的に生体情報を獲得するための様々な機器が開発されてきた。とりわけ,ウェアラブル端末を用いたアプローチは,非侵襲的で望ましいが,新生児の皮膚は非常にもろく,柔らかい。そのため,愛護的で持続使用可能な,次世代のインターフェースの開発が必要不可欠となる。
以上のような背景を元に,我々,横浜国立大学太田裕貴研究室と横浜市立大学伊藤秀一主任教授率いる小児科グループは,新規医療用IoTデバイスの開発を行っている。本論では,新生児医療用IoTのインターフェースの1つとして開発した経時的黄疸計測に向けたウェアラブルな光学式柔軟センサの開発を論ずる。
黄疸とは血中ビリルビンが何らかの疾患により皮膚や血管などに沈着した結果,皮膚や眼球が黄色く染まる病態である。ビリルビンには間接ビリルビンと直接ビリルビンがある。そのどちらが過剰であるかを測定し,黄疸の原因を推測する。直接ビリルビンが過剰な場合は,胆道閉塞,胆汁うっ滞,肝炎などの肝胆管系疾患が原因として考えられる。間接ビリルビンが過剰な場合は溶血性疾患,非代償性肝硬変,末期肝不全,体質性黄疸,母乳性黄疸が原因として考えられる。以上は一般的な黄疸に関する概要である。新生児に関する黄疸は上述とは異なる。出生5日後までの新生児は黄疸になりやすく,日本人では98%の新生児,白人では約60%の新生児が黄疸の症状を発する。
また,出生時体重が低いほど黄疸が現れやすい。胎内における胎盤を介した呼吸は,出生後の肺による呼吸と比較して酸素化の効率が悪い。そのため,胎児の血液中のヘモグロビン濃度は成人の1.5~2倍程度あり,さらに赤血球のヘモグロビンは胎児型のヘモグロビンFが主体で赤血球の寿命が短い。出生後,肺呼吸の開始とともに,過剰なヘモグロビンは分解され,その分解産物として大量のビリルビンが発生する。しかし,新生児は肝機能が未熟で間接ビリルビンを直接ビリルビンに変える速度が遅く,さらに消化管からのビリルビンの再吸収も多いため,大量のビリルビンを十分に処理できない。その結果,新生児の血液中の間接ビリルビン濃度が上昇し,黄疸が発症する。多くの新生児においては,皮膚の黄染を認めるものの生理的範囲にとどまり,医学的問題は発生しない。
しかし,一部の児においては,ビリルビン濃度が安全域より高値になり,ビリルビンが脳に沈着し,神経学的後遺症を呈する核黄疸を生じる危険性がある。新生児の生理的な血中ビリルビン濃度の上昇は生後5日後まで続き,生後日数と出生体重ごとに治療介入すべき基準値が設定されており,それを超えた際には光線治療や交換輸血などの治療を行う。そのため,新生児血液中の総ビリルビン濃度上昇を経時的に測定する必要がある。しかし,間接ビリルビンの血中濃度は,直接測定できないため,間接ビリルビンと直接ビリルビンをあわせた総ビリルビンの濃度で治療実施基準値が定められている。