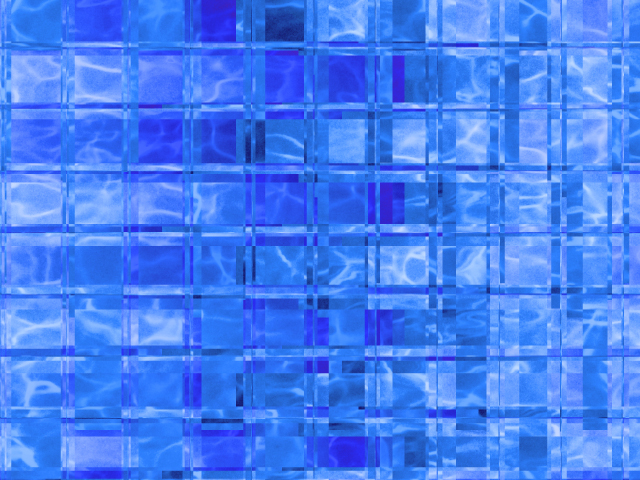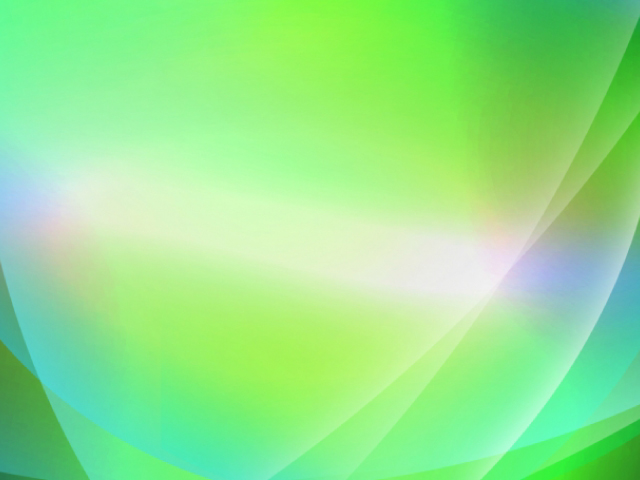1. はじめに

近赤外光(波長約0.7〜2 μm)は,生体への非侵襲性,高透過性を活かして医療・生体イメージング用のプローブ光としての利用が進んでいる。特に波長0.7~1.3 μm程度の領域は,生体に多く含まれるヘモグロビンと水による光吸収が少なく透過性が高いことから「生体の窓」と呼ばれ,医療・生体イメージングに有用な波長帯と考えられている1)。光コヒーレンストモグラフィ(OCT)は,この近赤外光プローブを用いた断層イメージング技術として知られる。
1990年代初頭に原理提唱2)されてから僅か数年の間に眼科臨床応用がなされ,現在は循環器や消化器といった様々な部位への展開が進められている。X線CTやMRIに比べ,侵襲性が低く,装置の小型,軽量化が可能であることや,光情報通信分野で熟成された光デバイス技術の転用が可能であるため,急速な発展と拡がりを見せている。OCTはマイケルソン干渉計を基本構成とし,光源に広帯域(低コヒーレンス)光を用いた低コヒーレンス干渉法によってサンプル内部の非破壊・非侵襲な断層画像取得を可能にする。
詳細な原理は後述するが,OCT光源の特性(中心波長および帯域)とOCT画像の光軸分解能は密接な関係があり,OCTの高性能化には適正な光源開発が重要である。OCTに求められるスペックの指標の一つとして,単一細胞の識別が可能な光軸分解能5 μm以下が挙げられ,「生体の窓」領域の中心波長を有する光源でこの分解能を実現するには,帯域が約100 nm以上必要になる。
これまで様々なOCT用光源の開発が行われているが,一般的な市販OCTには半導体材料をベースとしたSLD(Superluminescent diode)光源が用いられることが多い。SLD光源は,半導体の自然放出光を増幅しながらレーザー発振を抑制した端面出射型のデバイスであり,発光ダイオード(LED)とレーザーダイオード(LD)の中間的な特性(広帯域かつ高輝度)を持つ。LDと同程度のスポット経に集光可能であるためファイバー結合性が高いことや,軽量・コンパクトで低コスト化が図りやすく信頼性も高いといった特長があり,OCTの最大の利点である装置システムの小型化に大きく貢献している。
しかしながら,SLDの発光帯域は数十nm程度で,100 nm以上の広帯域化が難しく,市販OCTの光軸分解能が10~20 μm程度に制限される理由の一つとなっていた。我々はこの課題を解決する材料として,半導体ナノ材料である自己組織化InAs量子ドット(QD)3)を用いたSLD光源開発を行っている4〜8)。本稿では,そのInAs-QDをベースとした近赤外広帯域SLD光源の開発と,OCT光源としての性能評価結果について紹介する。