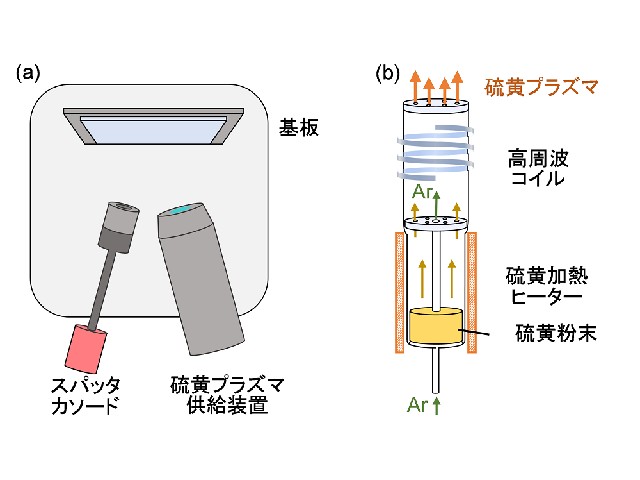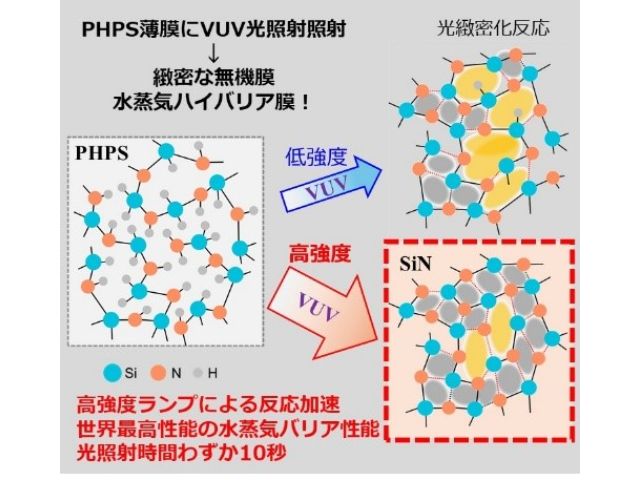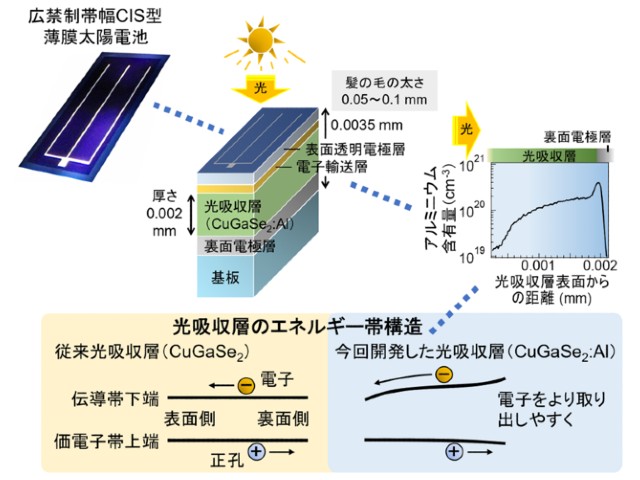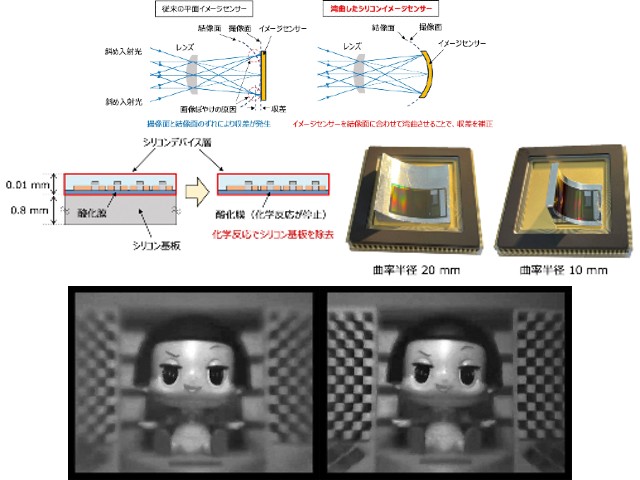理化学研究所(理研)染谷薄膜素子研究室(所属長:染谷隆夫 主任研究員)研究員の福田憲二郎氏は,非常に薄くて伸縮自在な有機太陽電池を作製したと,5月30日に開催された科学技術振興機構(NEDO)の新技術説明会で発表した。
理化学研究所(理研)染谷薄膜素子研究室(所属長:染谷隆夫 主任研究員)研究員の福田憲二郎氏は,非常に薄くて伸縮自在な有機太陽電池を作製したと,5月30日に開催された科学技術振興機構(NEDO)の新技術説明会で発表した。
有機材料はフレキブルで印刷による回路作成が可能という特長から,肌に貼ることができる有機ELディスプレーやセンサー,柔軟なボディを持つソフトロボットなどが提案されている。一方でその実用化には,同様にフレキシブルで軽量な電源が必要求められていた。
今回,福田氏らは有機材料である高分子ポリマーを利用し,薄くて軽い,伸縮自在な太陽電池を開発した。具体的には,厚さが1㎛(食品ラップの約1/10)の基板フィルムに透明電極,有機活性層,電極,封止材などを積層し,全体の厚さ3㎛を実現した。この太陽電池は文字通りクシャクシャに縮めても使うことができるため,上記のようなフレキシブルデバイスの電源としての応用が期待される。
この太陽電池を実現するカギとなった技術は2つある。その一つが理化学研究所 創発物性科学研究センター(CEMS)創発分子機能研究グループの瀧宮和男氏らが開発した有機太陽電池の活性層材料「PNTz4T」だ。これはガラス上で太陽電池を作成すると10%を超えるような変換効率を示すなど,世界最高の有機太陽電池材料の一つであるという。
もう一つは太陽電池を支持ガラス上に作成し,最後に剥がすという作製プロセス。フッ素系の樹脂を支持ガラス上に塗布することで,作製した太陽電池を支持ガラスからきれいに剥がすことを可能とした。これにより,扱いの難しい薄膜をガラス上で安定して作製することができるようになった。
基板にはパリレンに樹脂を塗って平滑化したものを用いた。透明電極としてITO,電荷注入層にはZnOを積層し,その上に活性層としてPNTz4TとPCBMをブレンドしたフィルムを付け,さらに電荷注入層として酸化モリブデン,上部電極として銀を製膜している。最後に素子全体を再びパリレンで覆って封止した。最高プロセス温度は170~180℃となっている。
伸縮自在を可能とするために福田氏らは,構造体のひずみの中間位置がくる位置を計算によって導きだした。ひずみ中間位置とは,どんなに変形させても面にストレスが加わらない位置のこと。各層の厚みやヤング率をコントロールすることでひずみ中間位置を活性層の真ん中に配置し,引っ張っても曲げても,計算上は活性層の面にひずみがかからない構造を実現した。
これにより,作製した太陽電池は支持ガラスから剥がしても性能は殆ど変わらず,剥がす前に8.0%だった変換効率は剥がした後も7.9%と,ほぼ同程度を維持することに成功した。
伸縮性を実証する圧縮試験は,伸ばしたゴムにこの太陽電池を貼付け,戻る力で半分程度に潰す方法で行なった。曲率10㎛以下のシワが蛇腹状にできた状態で変換効率を調べたところ,太陽電池が潰れたことによる受光面積の減少と,電流値の減少が高い一致を見せた。
さらに,この伸縮を20回程度繰り返しても変換効率は最初の状態から殆ど変化しなかったことから,この太陽電池は伸縮させたとき,受光面積の変化による発電量の減少あっても太陽電池としての性能の劣化は無いことが分かった。
試作した太陽電池のサイズは約25mm×25mm。これを複数組合わせた約50mm×50mmのモジュールの作成にも成功しているという。
福田氏は,上述の応用の他にも超軽量・フレキシブルな特長を活かし,衣服への貼り付けや無知覚な健康状態のモニタリングデバイス,さらには動物や家畜にセンサーと共に張り付けることで生態系のモニタリング,また曲面にも貼り付けられるので,ドローンの電源としても期待する。
最大の課題としてガスバリアの大気安定性があり,変換効率の経時劣化は700時間(30日)で50%となっている。これについては今後研究の必要があるものの,この数字ならば用途によっては十分使える可能性もあるのではないかとしている。他には変換効率の改善と共に,多様な環境下での駆動安定性のデータの取得,大面積化,大量生産化技術の開発などの必要があるという。
染谷氏は東京大学の教授も兼務しており,その研究室でもフレキシブルデバイスの成果を数多く発表していることから,これらを組合わせることで,さらに人体との親和性が高いウェアラブルデバイスの登場が期待できる。
関連動画
[vsw id=”bbYdw1G1pvk” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]