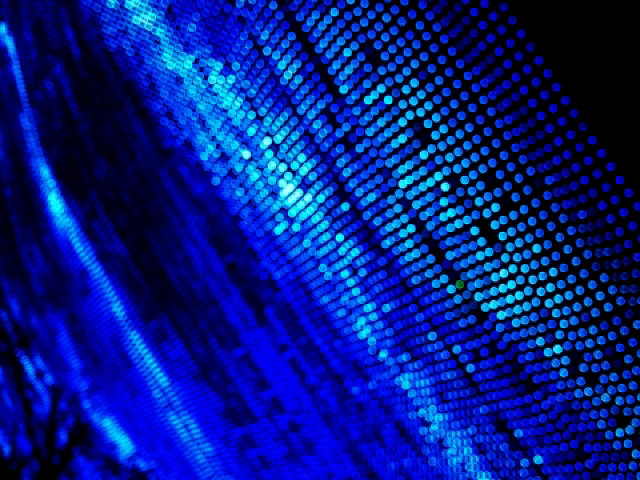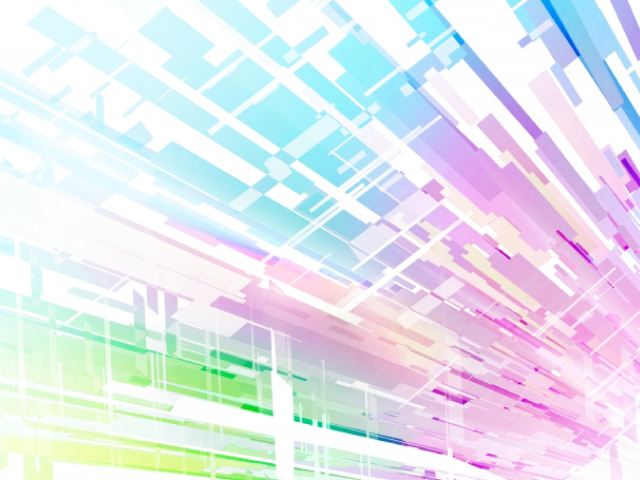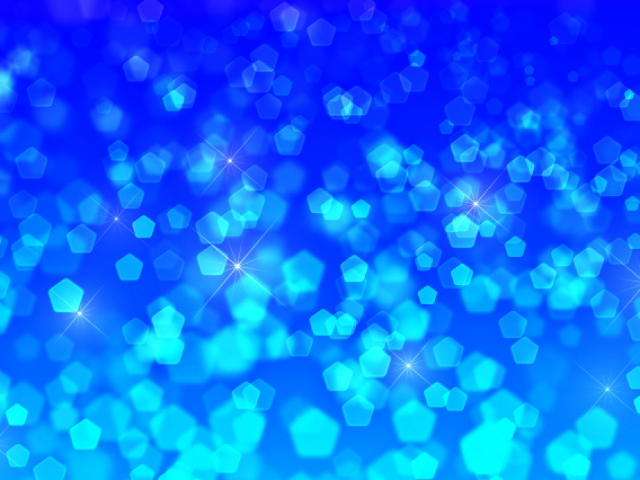4.2.6 波面収差
縦収差から横収差まで,我々は光線の数を増やしながら収差を評価してきた。Sagittalとmeridional結像の利用は今のような計算機のない時代の最大の工夫であったと言えよう。ただ,この両者で収差を表わしきれるかというと,実はもっと沢山の光線を扱うことが必要になる場合がある。MTFやspot diagram,パーシャリーコヒーレント結像計算で瞳面全体の情報が必須となるのは,前章までの議論から自明であろう。
瞳面内の沢山の情報をフル活用している典型例は大型天体望遠鏡のミラーである。直径8.2 mのすばる望遠鏡では姿勢の変化に伴う重力変形や,空気揺らぎ補正のために261本のアクチュエータが主鏡の下に配置され,鏡全体の形状を制御している。589 nmの光で発光させるガイド星を用いる補償光学については1.2.1項でも紹介したが2022年に光源が4 Wから22 Wに高出力化された。
波面収差までの分析が必要なのは顕微鏡や,半導体露光装置が主である。しかし,結像の光学的意味を理解する上で,波面の考え方は非常に役に立つ。
この続きをお読みになりたい方は
読者の方はログインしてください。読者でない方はこちらのフォームから登録を行ってください。