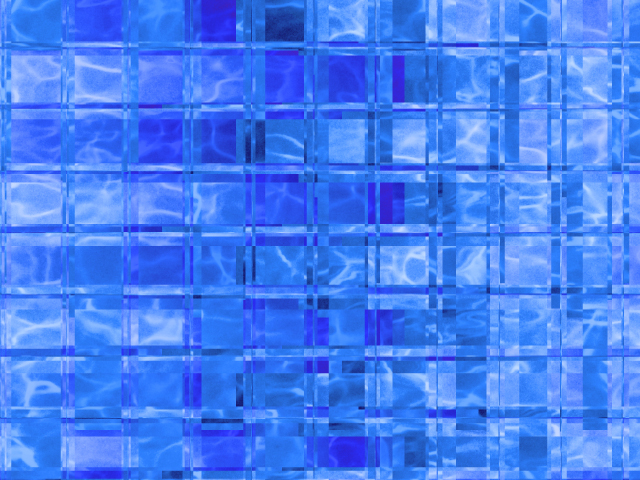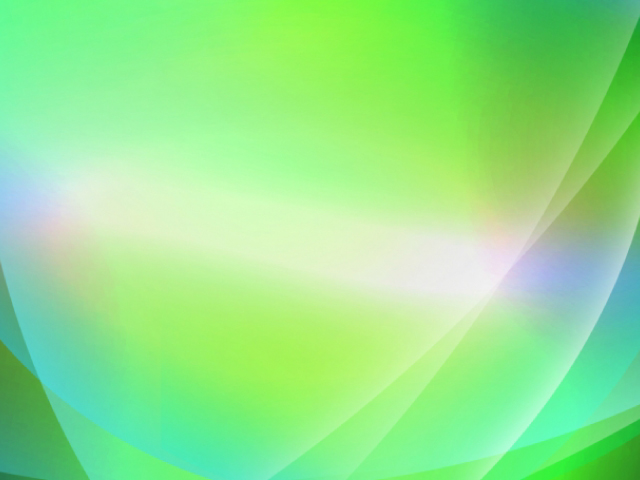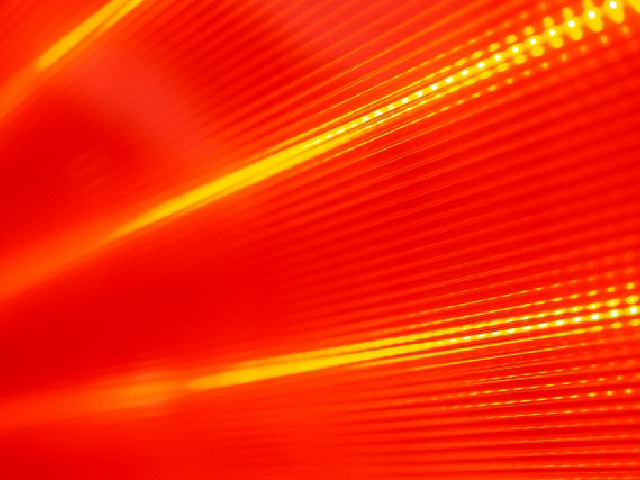1. はじめに

光を使ったバイオセンサーは反射率や透過率,蛍光(化学蛍光を含む),ラマン散乱,分子の赤外吸収を測定する方法など種々あり,バイオセンサーのなかで多数派を占めている。最初に歴史的な経緯から振り返ってみよう。
表面プラズモン共鳴(SPR)法は1990年頃にマイクロ流路と組み合わせる測定配置が確立し,安定的な測定が可能となった1)。この方法はSPR付近の波長域における反射率変化を観測するもので,典型的な検出限界は1μg/ml程度(モル濃度へ大まかに換算すると,数nM程度。M=mol/l)である。
さらに高精度の分子検出法として,酵素を援用した免疫検定法であるエライザ法が開発され,検出対象分子に標識された酵素によって増殖する副次生成物の濃度を透過率または化学蛍光を測定することで高感度化を実現した。現在の医療診断の標準的な分子検定法として用いられている。この方法の検出限界は,市販キットによって,幅があるが,典型的な最良値は1 pM程度であると認識されている2)。
ここで注意が必要なことがある。サブpM以下の極低濃度域における検出限界は,決め方が統一されておらず,報告例によっては分子濃度と検出信号強度を両対数プロットした標準曲線がべき乗でスケールされる範囲からずれ,さらに対象分子が存在しない場合の信号と統計誤差内にある測定点をもって検出限界と主張することが慣習化している。このようにして決めた検出限界は,実際の医療診断のための分子検定のなかでは信号ゼロの状態と区別できないため,有意の値とは言えない。
このような事情を考慮して,以下では,標準曲線がべき乗でスケールされている範囲の測定最低濃度を定量検出範囲の下限と呼ぶことにする。この基準では,過去の報告例で主張されている検出限界は,1桁から2桁小さい値を主張していることになる。このような過剰で実用性を損なう主張を是正することが,バイオセンサーの健全な発展に有益であると考える。
さて,ラマン散乱も高感度な分子検出手法として知られている2)。単一分子分光が可能な方法として,1997年の論文4, 5)が大きな注目を集めたが,20年以上経た現在においても分子検定法として実際の検査法として用いられていない。理由として,まず,単一分子からのラマン散乱信号を再現することが難しいということがある。そのほかにも,バイオマーカー分子は分子量が10万以上の巨大なタンパク質分子であることが多く,巨大分子の分子振動を検出したとしても,振動モードの同定することは一般に困難であることが理由として挙げられる。
近年,マイクロRNAのような小分子の検出も注目されており,この目的にはラマン散乱が有効である場面も考えられるが,マイクロRNAは塩基配列の差異がごく僅かな分子が多数あり,それらを分子振動で明確に区別できることを示す必要がある。そのうえで,蛍光検出など競合技術との比較検討において,明確な優位性がないと実用展開まで結びつくことは容易でないと考えられる。
蛍光分子は量子効率が高く,観測が容易な分子である。バイオ分子に蛍光を標識する技術6)が確立したため,今日では細胞や生体組織を染色して蛍光観察することはバイオ分野の標準手法となっている。蛍光標識したバイオ分子を検出する蛍光検出法も標準的な手法の1つであり,その感度が数あるバイオセンシング法のなかでも特に高いことが知られている2)。先述の化学蛍光を用いたエライザ法も広義には蛍光検出法の1つと言える。通常,光バイオセンサーはマイクロウェル上に対象分子を固定して検出する。
マイクロウェルは,対象分子の固定する目的に使用され,プラスチック製でそれ自体が安価であり,使用する試薬が少量でよいことが利点である。もしマイクロウェルの代わりに蛍光を増強できる基板を用いることができるとしたら,その増強度に応じて,より低濃度の対象分子を検出できることになる。しかしながら,増強度が1000倍を超えて顕著に蛍光を増強できる基板は数えるほどしか報告例7〜10)がなく,それらは蛍光信号の均一性が低い,つまり,再現性が低いという難点を抱えていた。
この数年来,筆者はメタ表面の研究に従事し,蛍光増強性能に特に優れ,再現性も高いメタ表面を見出してきた11〜14)。以下では,蛍光検出性能に優れるメタ表面(2節)とそれらを活用した蛍光検出バイオセンサーの研究開発に関する最近の進展(3節)について述べる。